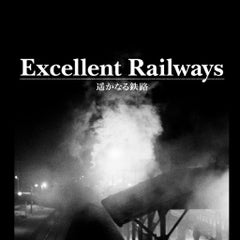「伝説の○○」、特に○○が車両や列車である場合は、動態保存ではなく、通常運用されていたものをいうことが多い。しかし、動態保存でも今や伝説となっているものがあると思う。一つは、1988年春に復活したC62 3によるSLニセコ号。これは誰しも異存はないだろう。熱狂的な信者を生み出した同列車は1995年秋に惜しまれながら運転を終えた。もう一つは、1990年から2006年までの冬季に磐越西線郡山〜会津若松間でD51 498により運転されたSL磐梯・会津路号ではないかと僕は思っている。
この列車の伝説たる所以は、①往路復路とも運転区間に急勾配があり、必ず爆煙に巡り逢えること、②積雪期の運転であること、③上下列車とも正向き(チムニーファースト)運転であることなどである。
SL磐梯・会津路号は1990年のウインターシーズンに突然登場した。この頃はいわゆるジョイフルトレインの全盛期で、事前に運転区間・時刻等が趣味誌に掲載されていた。しかし、SL磐梯・会津路号はそのような事前告知はなかった。当時の愛読誌『Rail Magazine』1990.4 No.77(1990年2月21日発売)には「「SL磐梯・会津路号」の運転情報に関しましては、正式発表が先月号締切後となったため誌上に掲載できませんでした。」という編集部の断り書きがある。そんな中で、僕がどうして運転情報を得ることができたのかは今となっては思い出せない。
↓『Rail Magazine』1990.4 No.77の表紙。試運転期間中は現役時代を彷彿させる車番が大書されたスノープローを装着していたが、本運転では車番表記は消されてしまった。どうやら字体が綺麗すぎると不評だったらしい。現役時代は殴り書きのような手書きだったのである。
兎にも角にも何はともあれ万難を排して駆けつけなければならないと思ったことはいうまでもない。試運転は1月29日(月)から2月1日(木)までの四日間、本運転は2月3日(土)と4日(日)の二日間である。試運転は平日であり仕事の都合上出撃不可だったので、本運転に駆けつけた。泊まりがけで行ってもよさそうだが、なぜか日帰りだった。
(注・出撃したのが2月の3日だったのか4日だったのか覚束ないが、ネットにある動画の天気から察すると4日のような気がする。)
現地へはマイカーで向かった。ノーマルタイヤだったので、郡山ICを降りたところでゴム製のタイヤチェーンを取り付けた。
まずは磐梯熱海と中山宿の間にある片築堤に行ってみた。下から見上げて撮るか、築堤を登った線路端で撮るか迷ったが、多くの同業者がいる上で撮ることにした。ただ、出足が遅かったこともあり、前列でカメラを構えることは難しそうだったので、脚立を担いで築堤を登った。しばらく待つと遠くで汽笛が鳴り、徐々にドラフト音が近づいてくると、山影からデコイチが姿を現した。予想に違わずいい煙だった。
↓磐梯熱海から中山宿に続く25‰の勾配を登るデコイチ。当時はビデオをメインに撮影していて、スチールは予備の位置付けだった。そのため、フレーミングも厳密ではなく、編成後端が切れてしまっている。(磐梯熱海〜中山宿)
↓2発目は翁島のハズレで煙を期待してカメラを構えた。(翁島〜更科(信))
さて、カット数を稼ぐだけならこの先も列車に追いつくことはできるが、磐梯町から先は下り勾配なので煙は全く期待できない。雪道を無理してまで追いかけることはやめて、ロケハンを兼ねてのんびりと沿線に車を走らせた。返しの列車は会津若松から磐梯町までの上り勾配区間が勝負なのだが、めぼしい撮影ポイントはどこも立錐の余地なく三脚が林立していた。
そこで天気が良くなってきたこともあり、磐梯山が見えるのではないかと行ってみると、ビンゴだった。上り勾配区間の喧騒とは無縁のマッタリとした雰囲気の中でデコイチを撮影した。
これにて撮影終了。スチールはわずか3カットであるが、ビデオの方もそれなりにいい絵が撮れ、来シーズンの運転を期待しながら現地を後にして帰路についた。
↓列車がくる頃になると磐梯山の頂が雲に遮られてしまった。鉄チャン界によくあるクルクモルである。(翁島〜磐梯町)