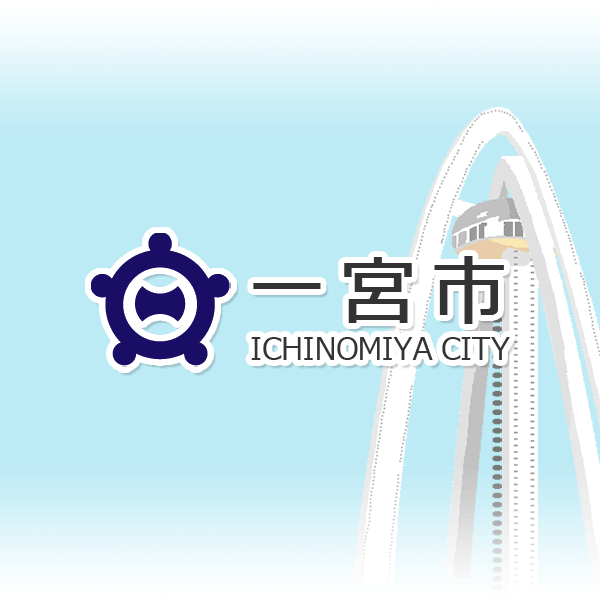/尾西歴史民俗資料館 名鉄 蘇東(起)線 展/ 25年2月8日〜3月16日
〜 起と一宮間の交通機関の歴史 〜
尾張地域の中核都市一宮市 宿場町や毛織物業で栄えた「起(おこし)」エリア(旧 尾西市、現在は一宮市に編入)と、東海道線尾張一宮駅を結ぶ路面電車があった
かつては熱田から桑名へ通じる東海道の宮宿と、大垣・岐阜から木曽路へ通じる中山道の垂井宿を結ぶ「美濃街道(美濃路)」の「起(おこし)宿」として賑わいを見せていたようだ
大正期に一宮と結ぶ軌道線「蘇東線(起線)」5.3km が開業(その後名鉄に編入)するが、1954(昭和29)年にモータリゼーションの波の中、バス転換されて廃止となった
その経緯もあって現在も名鉄一宮〜起 間のバスは頻繁に運行されています
ーー・ーー・ーー・ーー・ーー
車両は、木造ダブルルーフ・オープンデッキのモ40形(モ40〜43)、岐北軽便鉄道(のちの揖斐線)から転入したモ25形(モ25〜28)が使用された
(1946(昭和21)年頃の名鉄路線図)
1)官設鉄道から取り残された宿場町「起」
1870(明治3)年、明治政府の鉄道測量隊が、江戸時代の街道「美濃路」を通行するも、東京と京都を結ぶ官設鉄道が中山道経由に決定した 1886(明治19)年に建設資材運搬のため武豊から北上して木曽川駅まで開通し、一ノ宮(現在の尾張一宮)駅が開業する その後東海道経由に変更され、1889(明治22)年に東海道線新橋〜神戸間が全通し、一宮が貨客の集散の中心地となる
2)起軽便鉄道計画
東海道線が通らなかった起と一ノ宮駅を直接結ぶ起軽便鉄道計画が持ち上がり、地域の織物業者を中心に1914(大正3)年に敷設免許を申請するも却下される
3)蘇東耕地整理事業と蘇東電気軌道計画
明治・大正・昭和にかけて実施された蘇東耕地整理事業により、起と一宮を直線に結ぶ道路の一宮大垣線(今の通称起街道)ができた 起軽便鉄道計画の関係者を中心にした蘇東電気軌道発起人に、1921(大正10)年、起〜一宮間の起街道上の軌道(路面電車)敷設特許が下りる 1922(大正11)年、蘇東電気軌道株式会社が設立され、1923(大正12)年、名古屋鉄道と合併する
4)名古屋鉄道蘇東線から起線へ 〜 一宮にもチンチン電車が走っていた!
1924(大正13)年2月1日、名古屋鉄道蘇東線 起〜一宮(のち八幡町)間が開通、1930(昭和5)年、尾西線経由で 一宮〜新一宮 間が開通して全通した 1948(昭和23)年、蘇東線を起線に改称 1952(昭和27)年、尾西線が電圧を600Vから1500Vに昇圧して、新一宮に乗り入れできなくなったので、八幡町〜新一宮 間が休止となった 1953(昭和28)年、起〜八幡町 間が休止となりバス化され、1954(昭和29)年、起〜新一宮 間が廃止された
5)名鉄バス起線
現在でも、起〜一宮駅 間で最多は朝7時台と夕方5時台で各6本運転され、尾張中島〜一宮駅 間は蓮池行と西中野行が加わり、幹線バスとして重要な路線となっている
ーー・ーー・ーー・ーー・ーー