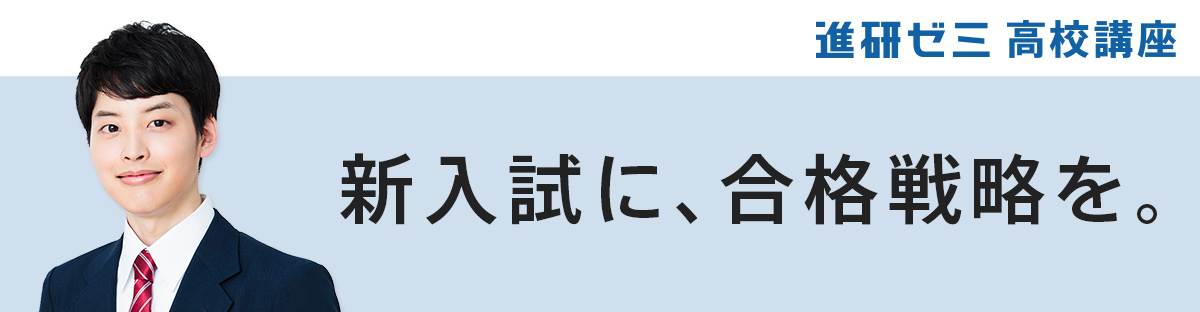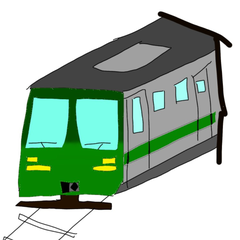2月22日にデビューする3200形だが、今年度は6両編成が1本導入された。2025年度にも増備されるとすれば、何両編成で登場するのか。
個人的な意見でしかないが、引き続き6両編成で導入するのがベストである。理由は2つだ。前提として、3200形の導入によって置き換えられるのは3500形で、3400形と3600形の置き換えは後回しにされるものとする。
1つ目の理由は、走行距離だ。3500形には4連と6連が存在するが、4連が走っているのは金町線と、日中の千葉・千原線のうちの1運用、日中の東成田・芝山鉄道のみだ。金町線は、たった2.5kmの路線であり、日中の1時間あたりの走行距離は1運用につき10kmで、ピーク時でも15kmだ。千葉・千原線は合わせて23.8kmだが、4連は日中の1運用のみだ。東成田線と芝山鉄道線は合わせて9.3kmであり、日中は40分間隔と本数が少ないため、4連の1運用で回せてしまっている。一方の6連は、京成本線と千葉・千原線の普通運用、本線の6連快速、日中時間帯以外の東成田・芝山鉄道など、4連よりも活躍の場が広く、走行距離も4連運用よりも長い。京成本線の普通運用で最もメジャーなのが、上野と津田沼の29.7kmを結ぶ運用だが、日中は40分に1本が臼井まで乗り入れており、京成上野から京成臼井までは45.7kmである。ラッシュ時間帯は、京成臼井よりも先の京成佐倉、宗吾参道、京成成田、芝山千代田、成田空港まで乗り入れる6連運用も存在し、当然そこに3500形が充当される機会も多い。3500形は車齢が50年を超えており、動力コストが大きい。3200形の導入によって動力コストを削減するのであれば、走行距離の短い4連よりも長い6連を先に淘汰する方が効果的である。
2つ目の理由は、3500形の4連はワンマン運転に対応しているということだ。京成電鉄では、いずれの路線も日中時間帯に限定されているが、金町線、千原線、東成田・芝山鉄道線において、3500形4連と3600形3668F(ターボ君)を用いたワンマン運転を行っている。ワンマン運転が始まったのは2022年の秋であったが、この時点では4連を組める新型車両が無かったため、車齢が50年に迫るような車両に無理矢理ワンマン化改造が行われた。せっかくワンマン運転に対応させた編成をすぐに引退させるのはさすがに勿体無いし、ワンマン運転に対応したことで人件費の削減に貢献した車両の置き換えを急ぐ理由が見当たらない。3200形では、ワンマン運転対応改造に向けた準備がされており、6連の3200形を増備すると同時に3000形にもワンマン運転対応改造を施せば、そう遠くないうちにワンマン化することが可能である。さて、2本だけ存在する3700形の6連はどうなるのだろうか。そもそも、京成電鉄が本線や千葉線の6連運用をワンマン化する気があるのかもわからないが。
京成は3100形の導入打ち切りを決めたようだが、3400形の置き換えを3200形で行うのは無理があるのではないか。3200形は2両単位で編成両数を変更できるため、8両編成とする場合は実に4両が運転台付きの車両となり、乗務員室部分のデッドスペースがあまりにも多く、乗り入れ先の地下鉄の混雑率悪化に拍車をかけそうだ。3100形は完全にアクセス特急向けの車両であるが、そもそも京成がアクセス線系統と本線系統で車両を分ける必要があるのかすら疑問である。何故なら、乗り入れてくる京急車と都営車は、本線とアクセス線系統の両方を担当しているからだ。車両を共通化したうえで、3100形をもう1編成増備してほしい。
3200形 市川真間駅
3500形 京成関屋駅
3600形ターボ君 京成金町駅
3600形リバイバルカラー 京成関屋駅
昨年の12月に全般検査を通ったので、引退はまだまだ先になると思われる。
3000形 京成関屋駅
3700形の6連は2本ともこの顔だ。
3100形 八広駅
3400形 船橋競馬場駅
 こどもちゃれんじベネッセコーポレーション子供の知的好奇心が刺激され、自然と幅広い知識を吸収するようになります。
こどもちゃれんじベネッセコーポレーション子供の知的好奇心が刺激され、自然と幅広い知識を吸収するようになります。 進研ゼミ 小学講座ベネッセコーポレーション私自身、中学受験経験はありませんが、某大手の個別指導塾でアルバイトをした経験から、進研ゼミでも中受対策は可能と考えます。
進研ゼミ 小学講座ベネッセコーポレーション私自身、中学受験経験はありませんが、某大手の個別指導塾でアルバイトをした経験から、進研ゼミでも中受対策は可能と考えます。 進研ゼミ 高校講座ベネッセコーポレーション日々の予習復習を効率良く行うことができます。高3からは受験に特化した教材となり、塾に行かなくても大学受験を突破できます。
進研ゼミ 高校講座ベネッセコーポレーション日々の予習復習を効率良く行うことができます。高3からは受験に特化した教材となり、塾に行かなくても大学受験を突破できます。 進研ゼミ 中学講座ベネッセコーポレーション日々の授業の理解はもちろん、テスト前も効率良く復習できます。塾に行かなくても余裕で高校受験を突破できます。
進研ゼミ 中学講座ベネッセコーポレーション日々の授業の理解はもちろん、テスト前も効率良く復習できます。塾に行かなくても余裕で高校受験を突破できます。