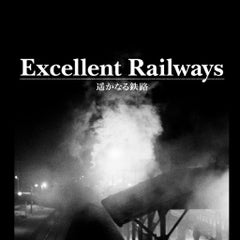かつて撮影した場所が今どうなっているか、Googleストリートビューで確かめるシリーズの第4弾はしなの鉄道(旧信越本線)。
1985年10月某日、上田交通別所線の撮影に出かけた。同線は翌年秋に架線電圧の昇圧が予定されていた。昇圧が実施されると、親会社の東急から中古の車両が大挙して流れてくることは火を見るより明らかだった。実際当時既に東急からは青ガエルこと5000系のサハを先頭車化した車両やデハ3300形を降圧改造した車両などが入線して運用に就いていた。しかし、同線にはそれよりも魅力的な丸窓電車(モハ5250系)が1928年製という高齢ながらも現役で走っていた。それをターゲットに訪れたというわけである。当時愛読していた雑誌『蒸気機関車』に撮影ガイドが載ったことも訪問を後押しした。
当日は日帰りではあったが、好天のもと別所線沿線のあちこちできめ細かく撮影し、それなりに満足できた。なので、まだ日は高かったが帰ることにした。上信越自動車道はまだ藤岡ICまでしか開通してなかった。往路は軽井沢経由で上田に入ったが、帰りも同じルートというのもなんだかなぁと思い、小海線に沿ったルートをとることにした。全くの気まぐれである。(なお、このとき気まぐれとはいえロケハンしながら帰路についたことが、1ヶ月後にサロンエクスプレス東京が小海線に入線した際の撮影地選定に大いに役立った。)
上田から国道141号を東進し、信越本線平原の手前で右折して県道137号に入った。右折してほどなくして信越本線を跨ぐが、跨ぐ際に線路をチラッと見て息を飲んだ。稲刈り後のはさがけが見事だったのである。そのまま車を走らせたが、こんな見事なはさがけにそうそうはお目にかかることはないだろうと思い直し、車をUターンさせた。
あいにく信越本線の時刻表やダイヤグラムは手元になかったが、当時の信越本線は特急街道。しばらく待てば『あさま』がやってくるはずと、三脚をセットした。果たしてすぐに『あさま』が通過していった。もう少し粘ってもよさそうだが、なるべく明るいうちに小海線を見ておきたいと思い、ごく短時間の滞在で現場を離れた。後日できあがってきたポジを見てとても満足した。拙著『Excellent Railways -追憶の鉄路-』に別所線の写真ともども収録した。
その後、信越本線を訪れることはなかった。第三セクター鉄道に成り下がった路線に興味を持つことはなかったのである。奇抜な塗装を受け入れられないこともあった。それが、近年115系がまだ残っていると知り、何かのついでがあれば立ち寄ってもいいかなと思うようになった。そこで、現地が現在どのようになっているのか、Googleのストリートビューで調べてみた。そして、あまりの変わりように驚いた。稲田はかろうじて残っているようだが、撮影した足場は整地され、外食店舗が何軒かあり、近くには葬儀場もできている。今でも鉄道を撮影できなくはなさそうだが、かつてのようなスッキリした写真は望むべくもないだろう。あのとき撮っておいてよかったと思う。
↓信越本線平原〜小諸にて
↓上の写真を撮影した場所の最近の様子。遠くに見える鉄塔の位置関係からして、ここで撮影したことに間違いないと思う。(Googleストリートビューより)
さて、ここからは余談になる。
そのまま国道141号を走っていると、野辺山あたりで日没が迫ってきた。野辺山駅に寄り道していこうかなどうしようかなと思ったその瞬間、僕は進行方向左手に真っ赤な小型DLがあるのを見逃さなかった。すぐにUターンしてそのDLに近づいてみると、それは酒井工作所製で、軌間は762ミリゲージのようだった。軽便車両がなぜこんなところにとまず思った。このへんにナローの路線はなかったはずである。でも、そんなことより、沈みゆく太陽光線がいい感じに赤いDLを輝かせている。氏素性のわからない車両ではあるが、ニコンとペンタックス6×7を取り出して、日没までのわずかな時間撮影に没頭した。その後しばらくこのDLのことは忘れていたが、1年後くらいに野辺山SLランドが開業したという記事を見て、あそこのことかと合点がいった。その野辺山SLランドも既に閉園して久しい。まさに今は昔である。
↑↓開業前の野辺山SLランドに佇む酒井製DL。本稿執筆に当たり調べてみると、同機は元上松運輸営林署の118号。氏素性がわからないどころか、木曽森林鉄道の車両なのであった。現在は岐阜県下呂市のひめしゃがの湯に保存されているらしい。ただし、色はグリーンになっている。
↓野辺山SLランド跡地。太陽光パネルが設置されている。(Googleストリートビューより)