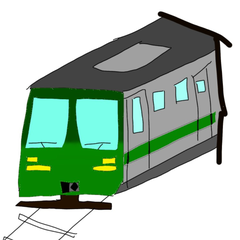来る2025年春、常磐線各駅停車と南武線でワンマン運転が開始される。JR東日本では2030年までに首都圏の主要路線の大部分をワンマン化する計画であるが、何故常磐線各駅停車と南武線がそのパイオニアになれたのかが気になった。そこで、素人目線で理由をいくつか考えてみた結果、3つ思いついた。
まず、前提としてワンマン運転を行う際には、運転席から客の乗降を確認できるように車両を改造する必要がある。首都圏の主要路線は言うまでもなく利用者が多いため、車両の改造に加えてホームドアを全駅に設置することが求められる。この点を理解した上で読み進めて頂きたい。
常磐線各駅停車と南武線は、武蔵野線を介せば乗り継げるが、直接乗り換え可能な駅はない。しかし、両者には意外な共通点があった。
①駅数が少ない
常磐線各駅停車は、運賃計算上は北千住~取手の路線だが、運行上は綾瀬~取手である。起点となる綾瀬駅は東京メトロの管轄駅であり、ホームドアも東京メトロによって設置された。つまり、常磐線各駅停車の駅は事実上、亀有~取手の13駅のみである。山手線の駅数は30、京浜東北・根岸線は47、中央・総武線各駅停車は39、中央快速線が24駅であることを考えると、かなり少ないことがわかる。
南武線の駅数は支線を除いて26だが、これは6両編成の駅が26個なので、このままでは先ほど挙げた他路線と直接比較することはできない。そこで、10両編成の駅何個分に匹敵するのかを計算してみよう。一次方程式の復習!10両編成の駅何個分に匹敵するのかを知りたいので、10両編成の駅数をAとする。Aについて以下の方程式を解く。
10両編成×A駅=6両編成×26駅
10×A=6×26
A=15.6≒16
南武線の車両の長さが常磐線各駅停車と同じだった場合、南武線は16駅ということになる。常磐線各駅停車と大差はない。
何が言いたいのかというと、駅数が少ない分、ホームドアの全駅設置という目標を達成するのに時間がかからなかったということだ。常磐線各駅停車も南武線も、2021年度以降にホームドアの設置が始まったが、たった数年で全駅への設置が完了してしまった。一方で、山手線と京浜東北・根岸線は、新型コロナウイルス感染症が流行る前からホームドア設置の動きがあったが、未だに未設置の駅が残っている。
②ワンマン運転対応改造の対象編成が少ない
常磐線各駅停車を走る車両はE233系2000番台が19編成、東京メトロ16000系が37編成、小田急電鉄4000形が16編成だ。このうち、JR東日本が改造を行うのはE233系2000番台の19編成であるが、このうちマト11編成が改造の対象から外されており、18編成である。この記事を書いている時点ではマト2編成が長野に入場しており、今後の動向が注目される。残りの車両のワンマン化改造はみんな乗り入れ先の私鉄に丸投げできるため、JR東日本にしてみればこんなに楽にワンマン化できる路線など他にないのだろう。
一方の南武線はE233系36編成のうち、N36編成を除いた35編成である。35編成と聞くと一見多いかもしれないが、南武線は6両編成であるため、全部で210両、すなわち常磐線各駅停車の車両21編成分であり、大した負担ではない。
E233系2000番台
東京メトロ16000系
小田急4000形
E233系8000番台
③混雑率が低い
通勤復活で「超満員」再び?鉄道混雑率ランキング 2023年度・100%以上の全国143区間を独自集計 | 通勤電車 | 東洋経済オンライン
2023年度における鉄道混雑率を見てみよう。2023年度に新型コロナウイルス感染症が5類に移行され、通勤利用もほぼ元どおりになっていた。
常磐線各駅停車の混雑率は、最混雑区間である亀有~綾瀬において133%である。一方の南武線は、武蔵中原~武蔵小杉で146%である。どちらも150%を下回っており、首都圏の主要路線でワンマン運転を行う上では良い実験台となるのだろう。