

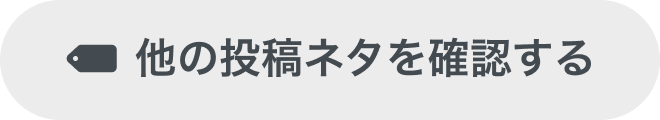
昔の方が便利だった点の多いものといえば、私的にはやはり鉄道、中でもJRを使った中長距離の鉄道旅です。
少なくとも今よりも、1980年代前半の国鉄末期から90年代後半のJR移行後10年ぐらいまでの間の方が、中長距離の鉄道旅を楽しむには便利で選択肢もそこそこあり、楽しかったように思います。
もちろん、新幹線延伸、湘南新宿ラインなど新しいルートでの直通運転の開始など、30~40年前と比較して便利になった部分はいろいろあります。
しかしその陰で、効率化や利用客減少、車両老朽化などを理由に切り捨てられていった便利な列車やサービスも数多く、そのことが本来は時代に合わせてブラッシュアップしながら残すべきだった鉄道旅の便利さや楽しみが損なわれていったことにもつながっていると思います。
例えば、特急列車も普通・快速列車も、在来線では運転系統が細かく分断されるケースが増え、JR会社間はおろか同じ路線の同じ県の中でさえ乗り換えを伴う異動が増えています。しかも、運転系統の区切り方も乗客の流れや利便性を考えたものでは必ずしもなさそうなケースもあるようです。
列車の運転系統の細分化は、効率的で地域の輸送の実情に合った施策といえば聞こえはいいですが、その背景には乗客の利便性やニーズとは関係のない鉄道会社側の事情というのも多分にあり、それがあまりにも前面に出すぎることで利用客にとっては不便さの方が目立ってしまっている気がします。
そして、最も昔の方が便利だったのは、夜の長距離移動です。
現在は定期列車としては「サンライズ瀬戸・出雲」しかなく、あとは観光列車やイベント列車の性格を帯びたものがたまに走る程度の夜行列車ですが、1980~90年代はまだまだそこそこ本数もあり、大都市はもちろん中小の街にも夜行列車でアクセスできる場所が結構ありました。それも一つの都市に対して複数の列車が設定されている場所も少なくなく、旅のスケジュールや好み、自分の懐具合によって列車や設備を選択することができたという点では、夜間の移動がほぼ高速バス一択になっている都市がほとんどの現在より数段便利だった気がします。
その他にも鉄道で「今よりも昔の方が便利だった」ことはまだまだあると思うので、また機会を見つけて書こうと思いますが、特に近年のJRは効率化や人件費削減などのコストカットに必死なあまり、必ずしも利用客本位とは言えない施策がかなり目立つ気がします。(京葉線などのダイヤ改悪や青春18きっぷのルール改悪など)
そのことが通勤通学などの日常的な鉄道利用に不便を生じさせるだけでなく、鉄道で旅をすることの楽しみもかなり失わせているような気がします。
思い出してみると、1980年代中盤からJR発足後6~7年後ぐらいまでの国鉄・JRには、それまでにない新しい列車や車両の運転や便利なサービスの開始など、少しでも便利で楽しい鉄道をつくっていこうという気概が今よりもずっと強く感じられ、それが私鉄などにも良い影響を与えていたように思います。
これからは昔のように鉄道の輸送量が大幅に伸びるなどということは期待できない時代になるけれど、そういう時代だからこそ今一度、鉄道で旅をしてみたいと思えるような列車や車両が続々登場してくることにも期待したいと思うし、人手不足や人口減少という時代であっても利用客にとって優しい鉄道であり続けてほしいと思います。
