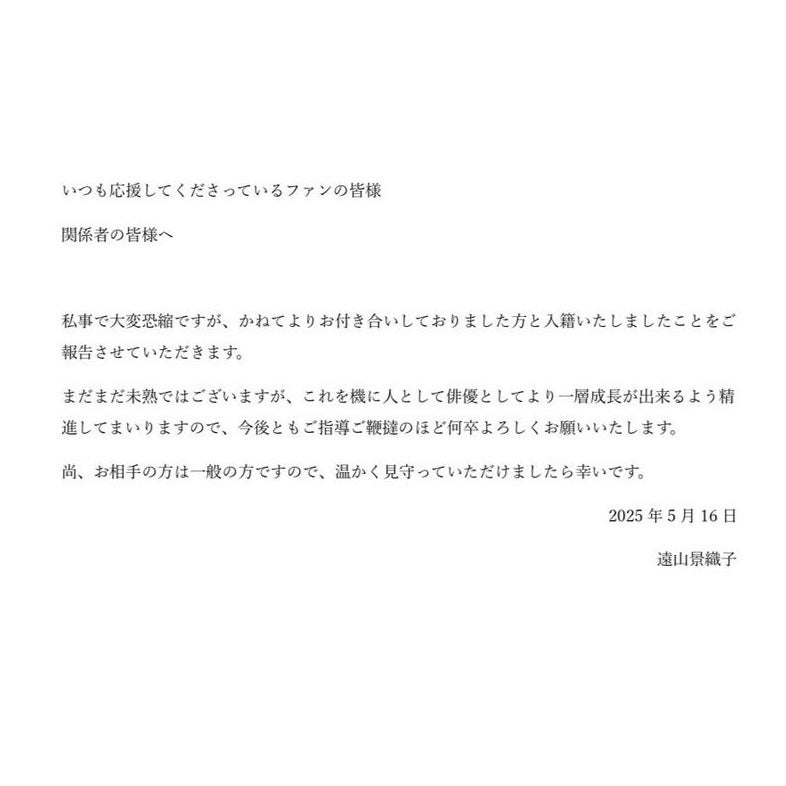今日はマイクロエースのマヤ34 高速軌道試験車です。車端部に自分で作った配管表現を更新し、チラつき防止のコンデンサーを入れました。
いつもご訪問頂きありがとうございます。以下本編です↓。
高速軌道試験車・マヤ34 2004が在籍、マイクロエースのA0304です。自連タイプのMicro Trainsカプラーに密連の先端を貼付けて双頭連結器を再現しているので、密連の連結機能はありません😅。今はED75 1037が牽引(BodyだけTOMIX、動力など他はほぼ全てKATO)しています。
撮影の機会が随分あったので模型在籍、写真は1番違いのED75 1038が牽引する”マヤ検”です。私は定期列車併結の姿は見たことが無く、全て機関車+マヤ1両でした。
この話はちょっと前に出て来たマニ30の話と絡んでいて..DCCでは製品のままだと台車スプリングが熱を持って周囲が溶けるので😅、KATOタイプの集電に改造して走っています。が特殊構造故、KATOのサスペンション機構に似せた構造にする”擬似サス化”が出来ていません。
なのでチラつき防止のコンデンサー仕込み対象です。開けてみると車長めい一杯にテープLED、右側に大型のブリッジダイオードを折り曲げるようにして詰め込んでいました。小型のブリッジダイオードに交換する手もありますが、矢印;集電用銅板の保持が弱くなり折れやすくなるのでこのままがイイでしょう。
端っこに場所の余裕が無かったので写真のようにど真ん中にコンデンサーを付けました😁。+側はテープLEDの端子に直接ハンダ付け、マイナス側は下側をテープで絶縁し、ブリッジダイオードのマイナス端子へケーブルを引っ張って取付けています。テープLEDには抵抗を介して給電していますが、その”下流”に付けるとチラつき防止の効果が激減するからです。
白色プラの天井板はコンデンサー部に切込みを入れて取付です。窓が無い位置なので目立ちません😁。例により47μFを2個です。
この車両は車端部に自分で付けた配管表現~1番下がそのままブレーキ管になってコックが無いのもマニ30と共通しています。
以下記事↓に載せた写真です。右4本、左3本の独特な配管を再現していましたが、何かイマイチ と書いてました😅。
TOMIXの配管付TNカプラーの配管部だけを使っちゃおうか?も考えたんですが、後部に向かい斜めに表現されているのがネック..
マヤ34の場合はほぼまっすぐ上に立ち上がらないと床下機器に当たってしまいます。
ということで自作のまま、作り直しをやっています。4本のウレタン被覆線(実測0.33mm径)を銅板に付けするのは一緒ですが、今回揃えて両面テープに貼付けてからハンダ付けする方法を思いつきました。この方が綺麗に出来ると思います。”両面”である必要は無いんですが、粘着力が高いからです😁。
曲げ加工をやって貼り付けました。連結器左右のエアホースはKATOのジャンパ栓パーツから切出したものでコックが無かったので
工芸社のものに交換して黒く塗って仕上げ、だいぶ良くなった気がします😁。連結器右側の”左コック”を再現できる手持ちパーツは工芸社だけでした。
この車両は現状片側だけテールライト点灯、配管表現付です。DCCでは消灯スイッチを付けないと両側点灯しちゃう😅、しかし3台車が密集して付いている車両なのでスイッチを付けるスペースに苦労する筈です。検討してみて出来るようなら手を付けようと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。