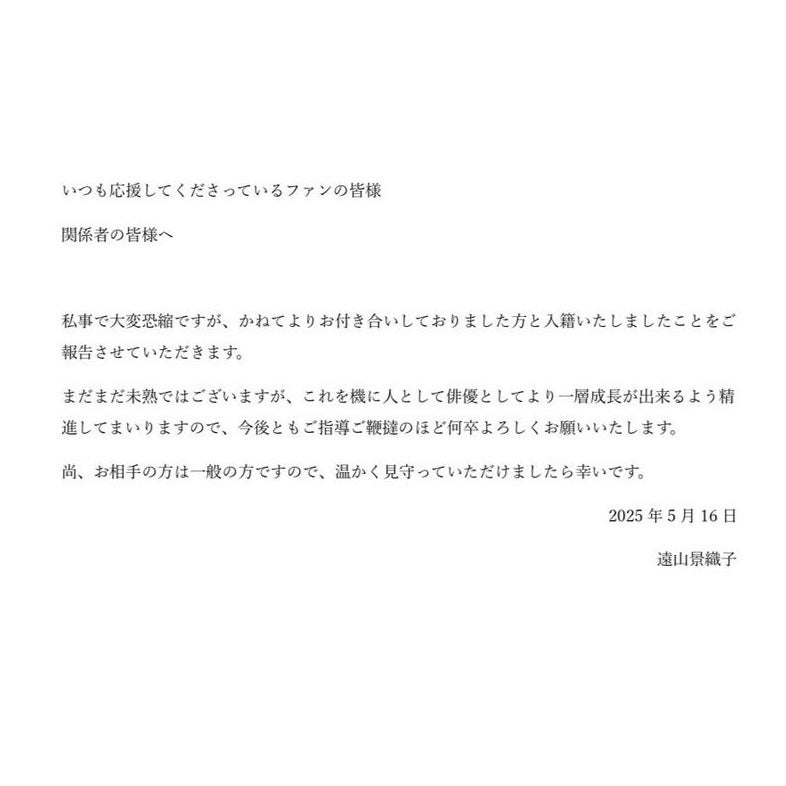今日はKATOの103系電車です。久々に整備再始動~今回は集電性能Upの”擬似サス化”をやります。今回で一段落となるので”擬似サス化”のやり方を今一度、少し詳しめに書いてみます。
いつもご訪問頂きありがとうございます。以下本編です↓。
整備ネタでは久々登場の103系、KATO 10-1743Cと1744C×2で10両編成を組んでいます。山手線の方向幕や、国鉄時代によく見られた適当にズレた運行番号表示など自作シールで再現しています。
今回は”擬似サス化”をやります。上がKATOの新仕様;サスペンション機構車(写真はオハ14 10-1438セットの1両)で矢印の部分で集電板が床下パーツに引っかかっている構造..文字通りサスペンションが効いて集電性能が高いです。下の103系は..
矢印で途切れていて引っかかりがありません。これだと集電性能が良くないのは経験多数😅、古い構造なんですが最近発売される車両にもシレっと混ざっていたりもします。これを自分でサスペンション機構車に似た構造に変えてしまおう です。似せて作るので”擬似サスペンション”、長ったらしいので”擬似サス化”です😁。
施工して行きます。台車集電部の穴を大きく拡げ、白色プラ板を貼ります。
白色のプラ板に集電板が引っかかるようになる..早速サスペンション機構車に似てきました😁。
穴の拡大は超音波カッター(手前)で大雑把にカットし、通常のNTカッターで四方を整形します。全部NTカッターでも出来なくはないかも知れませんが..アブナイ感じがします。特に数をこなすとどこかで手を切っちゃいそう😅。超音波カッターは他の模型弄りでも重宝しています😁。
集電板の長さが足りないので短くカットしてから両側にハンダ付け、元の集電板は0.15mm厚でしたが、サスペンション機構車は0.1mm厚なので合わせます。擬似サス化の途中からハンダ付けをやるようになったのは節約のためもありますが、長い0.1mm厚の燐青銅板を同じ幅でビシッと切り出すのがかなり難しい😅というのもありました。真っすぐハンダ付けするのにコツが要りますが、だいぶ慣れたと思います。GM(グリーンマックス)動力で安定走行させる工夫でもハンダ付けによる集電板ツギハギをやっています😁。
組み立てれば”擬似サス”車完成😁。電動車を除く9両に施工~結構な作業volumeになりますが、集電の安定性は向上します。それでもKATOの製品ほどビシッとは行かないので室内灯にコンデンサーを付けて補完しますが、今回はやりません。これで1編成(E26系カシオペア)を除き旧集電構造車の擬似サス化終了、1段落です。(殿堂入り車など一部施工対象から外した車両もあります)カシオペアはコンデンサー入れを先行させ、まだ集電に問題が無いので当面実施しません。
ここで103系整備を再始動させたのは..間もなくボディーがGM製に変わるからです😁。KATOの103系製品は廉価なのはいいんですがHゴムの出っ張り表現とかかなり古い形態のまま、他にも色々物足りないところがあるので、床下はKATOを使い、ボディーはそっくり交換になります。カプラーのボディーマウント化もやる予定なんですが、GMボディーが来てからにしたいと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。