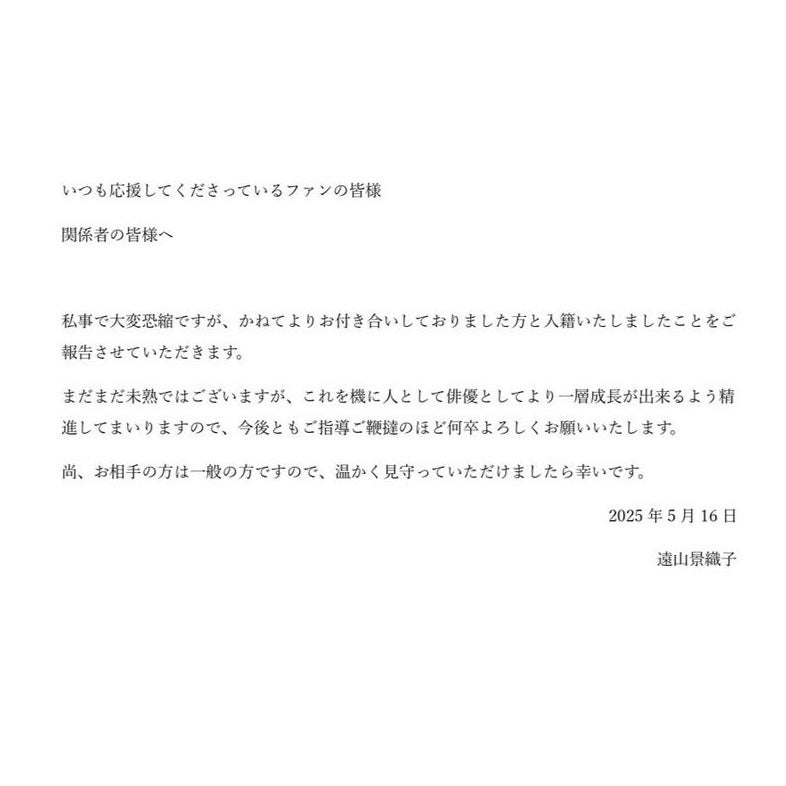今日は先日到着したKATOのデゴイチ、D51 397の話です。私の所はDCC化をしないと走れないので早速作業ですが、色々あるので2回に分け、今回は機関車本体側の加工について書いてみます。
いつもご訪問頂きありがとうございます。以下本編です↓。
DCC化を終えて走れるようになったD51 397(KATO 2016-B)です。左のC62 3 (2017-3)より一回り小さいのが分かります。ヘッドライトもDCC制御、On/Offが可能になっていますが、デゴイチの方が随分明るくなったな~😅。
今回は機関車側の話、DCCデコーダはテンダーに収めるので準備段階になります。KATO製の蒸気機関車は黒いダイギャストが左右分割になっていて、車輪に付いた軸受が接触して集電する構造です。しかしこの集電性能はあまり良くなく、テンダーと連結する通電ドローバーがダイギャストに接触して集電を助けます。(通電の導線は写真裏側です。)機関車本体だけで走らせると集電不良を起こしますから、テンダーの集電の方が効いていると思われます。
コアレスモーターは矢印部に入っていて、ダイギャストに挟み込まれた電極からリード線を介してモーターへ給電;つまり線路電源がモーター直結の構造です。
DCCでは線路電源とモーターの間にデコーダを挟んでいないといけないので電極をダイギャストから外し、テンダー側のデコーダから別に配線を牽いてやる必要があります。
通電ドローバーとは別に機関車とテンダー間を結ぶ配線が要る~ここが際どい所と思います。写真は切り離していますが、しっかり連結すると隙間は僅かですから..😅。13年前のC62 3は機関車側にデコーダを入れたので配線不要だったんですが、こちらも大変キワドく、無茶やってる感もあるので今回はテンダー側に入れてみます。DCCサウンドをやる場合も、皆さんテンダー側にサウンド機能付きデコーダとスピーカーを入れられているようですしね。
今回コネクター代わりに使うのは左のピンヘッダー(メス)です。右は前面展望動画撮影のCam Carに使ったZHコネクターですがそれよりさらに薄いものです。調べた限りで一番小さいものを買っていました。(余談;以前KATOホビセンの定員さんと会話した際、Big Boyはテンダーにデコーダーを仕込む改造をすればDCC化できるとのお話だったので、”そのためにはコネクターが要ると思いますが何か推奨のものはありますか?”と聞きました。が、明確な回答は頂けませんでした😅。)
6ピンだったのを切断して4ピンにし、モーターのリード線を内側2端子にハンダ付けしました。
続いてヘッドライト基板の加工です。矢印2か所にグラインダーを当てて絶縁し、チップコンデンサー?など不要な素子は取っ払って極細ケーブルをハンダ付けします。560Ωのチップ抵抗561が付いていましたが、明るすぎるだろうと思い2kΩ;202へ交換です。(最初に書いたようにそれでも明るすぎた?😅)
元あった位置にライト基板を残し、極細ケーブルを右へと伸ばします。
ウェイトに溝が彫ってあったのは有り難い😄、ケーブルの走路になります。もしかしてDCC改造をする場合を考えての溝なのかな~?😁。
ピンヘッダーの外側2端子に接続しました。ハンダ付け作業は周囲の部品を撤去して行います。間違ってハンダごてを当てたりしたら一巻の終わりですからね😅。
ケーブルを避けてボディーはバシッとハマり、運転台の下に4端子のピンヘッダーを仕込んで機関車側の対応終了です。(この製品、運転台の内部まで細かく作り込まれています😁。)なお、写真では通電ドローバーが下を向いていますが、連結状態ではピンヘッダーとの間に隙間は殆どありません。
ピンヘッダーに当たってしまうため、通電ドローバーの突起をカットしています。ちょっと危ないかな?と思ったんですが😅、今ならパーツも手に入る..と敢行、特に問題ないみたいです😁。運転台下(裏側)の突起もカットしてようやく収まったという感じです。(なおD51のAssy発売アナウンスがありません。2016-C;ギースルエジェクター発売後に出るのかな?と思っています。)
今回は肝心のDCCデコーダが出て来ませんでしたが😅、次回テンダー側加工の話で出て来ます。
最後までご覧いただきありがとうございました。