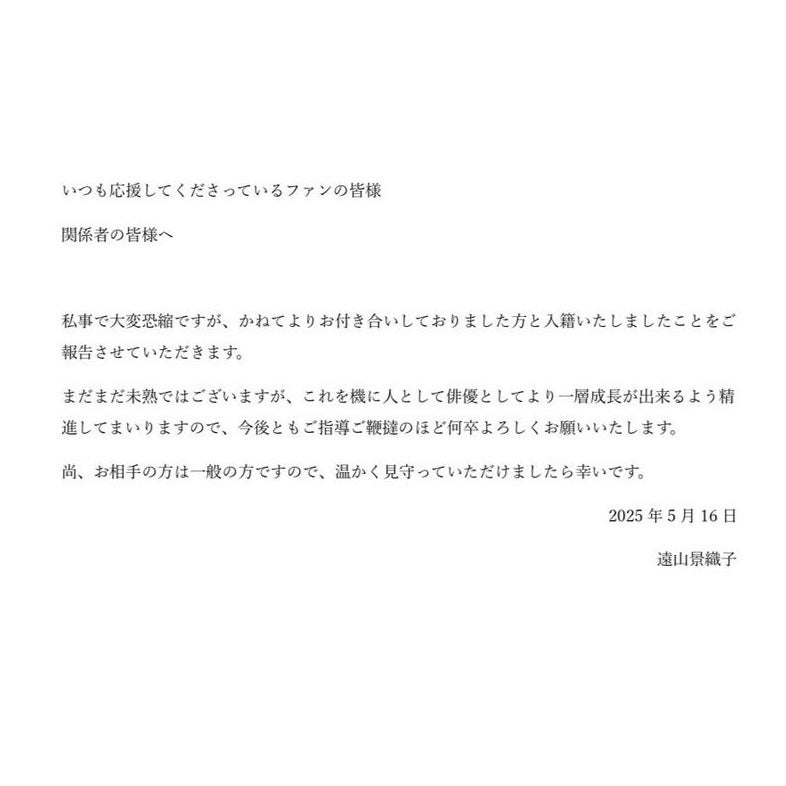今日はDCC車両検知の話です。大失敗をやらかして壊してしまったBDL168、機器の付け替えや検知区画の縮小などでフォローしようとしましたが、どうやらダメみたい..です😞。
いつもご訪問頂きありがとうございます。以下本編です↓。
前回↓基板上に線路固定の釘を落として正常検知が出来なくなったDigitrax BDL168です。
慌ててカバーを付け😅、矢印;事故を起こした位置は手持ちの正常動作基板(最初に買った51号機を52号機にアドレス変更)に置換えました。付近の配線変更中に起こった事故、作業はほぼ済んでいたのでスリカエです。
最初に買った51号機にはトランスポンディング機器RX4(白いの4つ)を付けて、対応する大型の木枠に納めていましたが、
壊してしまったものに置換(ロコネットのジャック上に51fと書いていますが元52号機)、RX4は付けている意味が分からなくなっちゃったので取り外し😅
BDLのケースを小さくして写真の位置(上)へ移設しました。ココの方が各検知区画への配線ケーブルが短くて済みます。余ったケーブルは他に転用します。
緑網掛付近に入れていた駅ホーム部車両検知の配線は、写真奥方に別途配線したので取り外し
ケーブル数が随分減ってスッキリしました😁。(ケーブルカバーを外して撮影しています。)
ダブルクロスの線路を切断し、矢印;固定式線路用の絶縁ジョイナーを小さくカットして入れる↓というやり方が1カ所増えて、左47、右49区画と細分化しました。
路線図左側にも検知区画を増設しようと思っていましたが中止、壊れたBDL168が検知を担当する電源区画は最小限にしましたが、左側;青網掛の7カ所が残りました。
釘を落としてから..BDLのアドレスは4(検知アドレスはLS49~64)、全て800番台で揃えていたので51へ変更操作をしましたが受け付けなくなってしまいました😅。
見た目は正常、緑のインジゲーターが点灯しますし、受け持ちの検知区間を列車は正常に走れるんですが..
肝心の検知が不安定😞、検知しないケースが発生します。写真はED75 145(DCCアドレス7145)を上5から自動運転中で黄色表示の15区画を走行中のもの、50電源区画で検知が働かないまま通過してしまったので、車両が通過したら消えて行く白い表示が残ってしまう ということが起こりました。こうなると1周して駅に戻っても正常な停止がかかりません。
検知せず通過したのはED75 145単機運転の場合、長編成の列車なら車輪数が多い分検知の”機会”が多いので大抵は検知してくれます。が、キハ58とか短編成列車(3両)もあるし、貨物列車は電流消費する検知車輪が間欠的で少ない、”自動運転をやるには全てがが完璧でなければならない”とmanualに書かれてもいるのでこれはダメだろう と判断しました😞。BDL168を1枚買い直し、壊れたものは自動運転をやらない区間で在線情報があった方が運転しやすい という所にサポート的に使おうと思っています。結局こうなっちゃったか😞、でも自分でミスったんだから仕方がない です😅。
最後までご覧いただきありがとうございました。