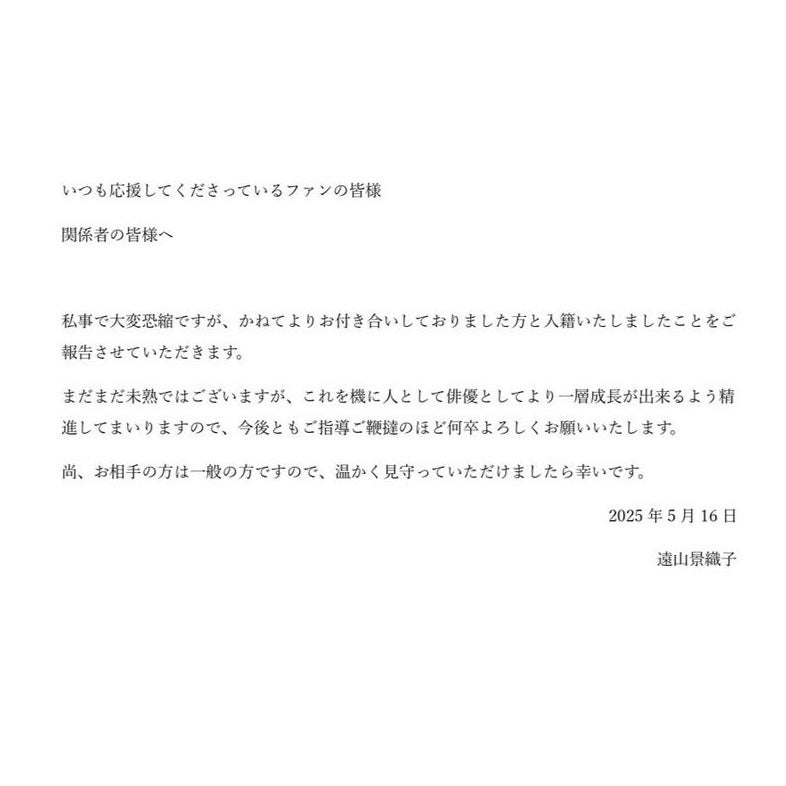今日はDCC車両検知~模型車両がどこに居るか検知する~の話です。配線変更の作業を進めたんですが大失敗をやらかし..恐らく検知機器の一部が正常に機能しなくなっちゃいました😞。
いつもご訪問頂きありがとうございます。以下本編です↓。
列車がどこを走っているか?停まっているか?を表示できるDCC車両検知機能~リバース共用区間やローカル駅付近の車両検知区画拡大をやって写真;JMRI路線図の右側に新たな検知区間が加わった所まで書きました。しかしまだ拡大することが出来るので今度は路線図左側 と思い作業を進めました。
これまでは路線図の駅左側、緑網掛け下に駅ホームの車両検知配線を入れていましたが
駅右側に改めます。丁度矢印;駅ホーム照明の給電端子(銅板を貼っただけ😅)があったので
その裏側、ホーム照明と一緒に車両検知の配線を詰め込めたのでラッキーでした。ケーブルを通しているのが1つ前の写真;緑網掛けの裏側になります。
元々計画していた作業です。当初は矢印など駅ホームの途中に何カ所かギャップを入れて区画を分けなければいけないと思っていたので右側にも..だったんですが、以下記事↓のように必要無いことが分かって来たのでギャップは入れません。
必要なくなり余った車両検知端子を使って検知区間を拡大しよう なんですが、写真の駅右側からレイアウト左方までケーブルを牽くととんでもない長さになるので、駅=1~6番線の検知配線を右に移し、左側を空けようという意図でした。車両検知機器;Digitrax BDL168にカバーが付いていますが、これが後述の大失敗に関係します😅。
加えてKATO4番ポイントの裏に青い車両検知用ケーブルを追加
ダブルクロスポイントの配線も一部撤去して”見えない”ギャップを切り
緑の短い検知区画を増設しました。手前の赤も短い区画になっていたので合わせた形です。赤線の奥側はリバース区画、リバースを出来るだけ長く取りたかったのでアオリを喰って短くなったんですが、
今までは図の58,59区画が一体で発車した列車がP29;No.29ポイントを完全に越える迄次の列車が発車できなかった所、短い58区画を作ったことで59区画に列車が居るうちに緑矢印のような発車が出来るようになります。
こうして作業しているうちに事件は起こりました。突然BDL168 1台(手前)が誤作動を起こしました。最初何で?が分からなかったんですが..
原因はBDL168基板上に線路を固定する釘が落ちていたこと..ヤバいところが短絡しちゃったんでしょう。やっちゃった~😞。(写真は基板を取り外し、無電源状態にしてからイメージ撮影をしています。)
まだ仮配線だからいいや と思っていたんですが、最初から基板の収納ケースを作っておかなきゃいけませんでしたね😅。慌てて写真のものを作って
 設置したんですが、一部端子の機能がおかしい~列車の走行は問題無いんですが肝心の車両の検知が不安定で列車が居てもセンサーがActiveになったりInactiveになったりするようになっちゃいました。大失敗だ~😞。
設置したんですが、一部端子の機能がおかしい~列車の走行は問題無いんですが肝心の車両の検知が不安定で列車が居てもセンサーがActiveになったりInactiveになったりするようになっちゃいました。大失敗だ~😞。
最悪は買い直しになりますが、今の所路線図左側に増設する検知区間の数を減らして対応しようと思っています。ややこしいフォローをやらねばなりません、なんてこった😞😞。(走っているのはED75 1036牽引、14系急行八甲田編成です。)
最後までご覧いただきありがとうございました。