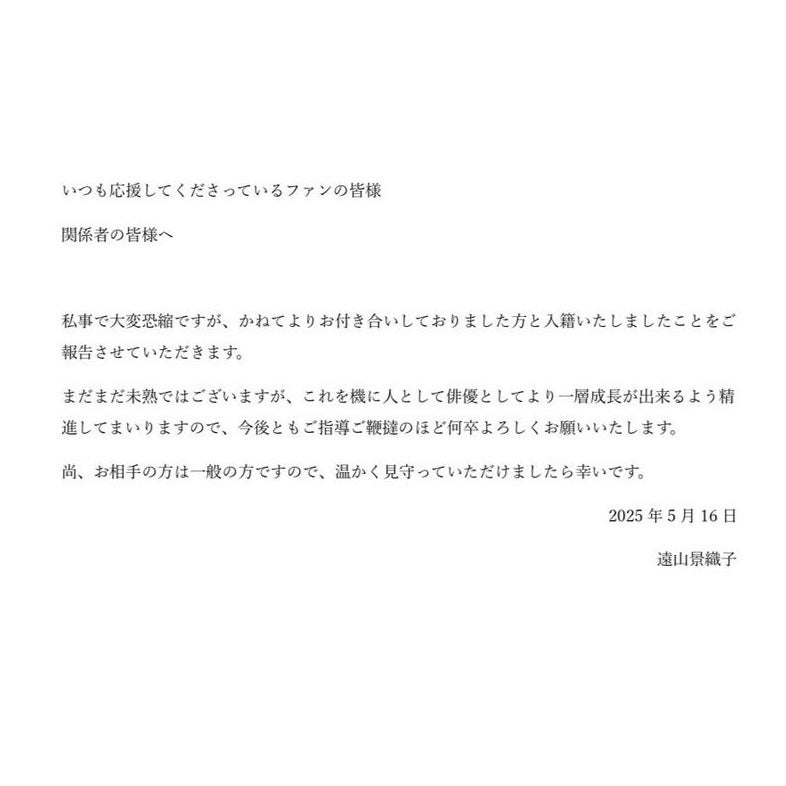今日はKATOヨ8000 車掌車の話です。最近再販された1両を増備しましたが、DCCで運転するにはあれこれ手入れが必要でした😅。自作室内灯など少し仕様変更もやっています。
いつもご訪問頂きありがとうございます。以下本編です↓。
KATOの8065 ヨ8000を1両増備しました。今回の再販から所属表記が天リウになったようです。
既存車は南ツソ、マイクロエースの特大貨物シキ800C編成↓に連結していますが、1両だけでは物足らず
2両体制となりました。左が新車ですが、DCCでは連結器だけ交換してすぐに走行 という訳には行きません。両側のテールライトが点灯しちゃうからです。以下記事↓と同じく手入れをしていきます。
内容は↑のリンク記事と被るのでサラッと書きますが😅、矢印の部分;床下タンク表現の窪みにミクロスイッチを仕込み、ケーブルを通す溝を2か所に掘って
ライト基板の一部を絶縁して、極細ケーブルを3本ハンダ付けして上述ミクロスイッチと繋ぎ..
ケーブルを引っ掛けないように注意しつつ難しい組立をこなして
スイッチ操作でテールライト片側だけ点灯、切換式に出来ます。カプラーもMicro Trainsに交換~↑リンク記事で1回やっていますから施工方法に悩むことはありませんでしたが、ここ迄険しい道程でした😅。このスイッチはon-onなんですが、慎重に中間で止めると両側消灯も出来ます。on-off-onのスイッチがあるといいんですが、長辺7mmほどのミクロスイッチにこのタイプの商品を見つけられていません。
室内灯も既存車と同じく自作、最初10μF×5のスティックコンデンサー×2を付けたんですが、チップLED1個に100μFは容量大きすぎ?..半分で十分なので、
片側を撤去して代わりに室内灯消灯スイッチを付けました。既存車も同じように仕様変更しています。
最近流行りの47μF(右)を使わず10μF×5スティックコンデンサーにしたのは高さの差、前者を付けると窓上部にはみ出して見えるようになっちゃうからです😅。白色プラの天井板を貼り付ける面積を稼ぐのにも好都合でした。今回片側がスイッチになりましたが、こちらも平たく面積があるので同じように両面テープで天井板を貼れます。なお、ヨ8000は屋根裏にもウェイトが仕込まれているので、ボディーと屋根の間に”挟み込む”作戦は使えません。
こうして手前のように全消灯~カマ次位や編成中間連結にも対応できるようになりました。室内灯のスイッチ操作はボディーを外して行う必要がありますが、これで精いっぱいと思います😅。
点灯で並べてみます。左が今回の新ロットで右が既存車、このテールライト明るさの違いは何なんだ??😲。既存車が暗すぎる...ライト基板のAssyを入手して交換してみる手もあるかな?と思っています。
2両になったので改番も必要~既に終わっていますが長くなるので次回にします。
最後までご覧いただきありがとうございました。