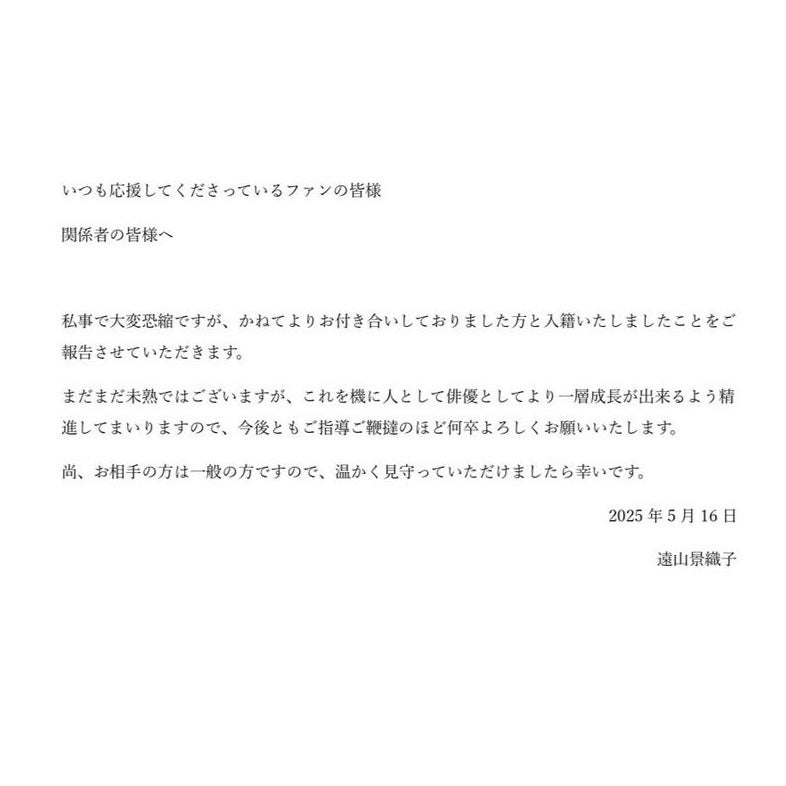今日はKATOの近鉄ビスタカー10100系の話です。変てこなタイトルになりましたが😅用意していた留置線の手直し、小窓から車内にケーブルが見えるのを解消、A+B編成運転をやり易く..と色々やっています😁。
いつもご訪問頂きありがとうございます。以下本編です↓。

再び登場の近鉄ビスタカー10100系、KATO 10-1911(A+C+B編成)、10-1910(C編成)の4編成12両が在籍です。写真では後ろの方が見えないんですが😅、これまでやっていなかったC+C編成とA+B編成を組んでいます。後述する話に関係します。

いつものパターンで😅だいぶ凝って弄りまくって以下記事↓で一旦整備終了でしたが、写真の矢印;小窓の向こうにケーブルが見えるのが気になると書いていました。
 ケーブルを写真奥側に寄せてプラ板の仕切り壁を貼りました。手前には小窓がありますが奥は機器室になっていたようなので必ず壁があっただろう と付けています。
ケーブルを写真奥側に寄せてプラ板の仕切り壁を貼りました。手前には小窓がありますが奥は機器室になっていたようなので必ず壁があっただろう と付けています。

これでケーブルが見えることが無くなりました。ちょい手直し程度、意外と簡単に済みました😁。

続いて4階層留置線の話です。以下記事↓は小田急NSEの長さに合った線形に変更し、奥にもう1編成停められるように..という内容でしたが、そのもう1編成は近鉄ビスタでした😁。ロマンスカーと同じく連接車両なので留置線を用意しようと考えたんですが、写真は手直し後の姿..
手直し前はA+C+Bの9両編成を奥の車止めにぶつけて停めても写真のようにギリギリ、飯田線旧国が何とかすり抜けますが、
これではキツイでしょう。(余談ですが私が
飯田線旧国を見ることが出来たのが1982年、近鉄10100系('79年引退)より長生きだったんですね😅。)
有効長をちょっと伸ばす工夫(写真右端)をしました。下のED62重連が走る線を通過する際パンタグラフを擦っちゃうので緑線のように斜めにカット、右端の車止めは左2本より手前にありました。それじゃ~有効長が厳しいので右の1本だけ延伸、薄い床板を使うことで頭を擦らないように配慮しました。ギリギリ編成が収まっていたのでちょっとだけ伸ばせればOKです。
予定変更で3両編成×4になっちゃったので、残り1編成は写真右側に停めます。空いていた留置線を活用、こちらも奥に延伸し6両分の有効長を確保したので6両編成×2本という留置の仕方も可能になります。
写真のように小田急NSEの脇を抜けて留置線に進入します。並ぶことは無かったであろう連接車同士が一瞬並ぶようになります。(NSEは写真のピントを出すため手前に停車、奥はまだ余裕があります😁。)
最後にA+B編成運転の話です。以下記事↓に書いたようにA+C+Bでの安定運転の為A編成のトラクションタイヤを1つ撤去して1カ所にしています(V13;C編成も)。これでは動力を持たないB編成と組んだ時にスリップして坂を上がれません。トラクション2か所で残したV18;C編成と動力台車を交換して運転する手もあったんですが、モ10300用の動力台車パーツ(14083D1)を買って来て..
A+B運転をやる時だけ、買って来た2トラクションの予備台車に交換して運転した方がシンプルだろうと考えました。
元々は他の車両と互換が効かない近鉄ビスタの予備パーツを持っておこうと買ったものですが、動力無しも含め連接台車の付け外しにはコツが要るみたい、矢印の部分を押さえて付けないと入らないし、入っても台車の左右振れが硬かったり..なので出来るだけ付け換えの機会を減らそうという考えでした。基本はA+C+B又はA+C/C+Bでの運転にしたいと思います。
上述動力台車の交換~A+Bの試運転をやったので動画にしてみました。先に通過するのが両端切妻のC+C、後から来るのが両端流線形のA+B編成になります。
どちらも快調に走りました😁。
最後までご覧いただきありがとうございました。
 ケーブルを写真奥側に寄せてプラ板の仕切り壁を貼りました。手前には小窓がありますが奥は機器室になっていたようなので必ず壁があっただろう と付けています。
ケーブルを写真奥側に寄せてプラ板の仕切り壁を貼りました。手前には小窓がありますが奥は機器室になっていたようなので必ず壁があっただろう と付けています。