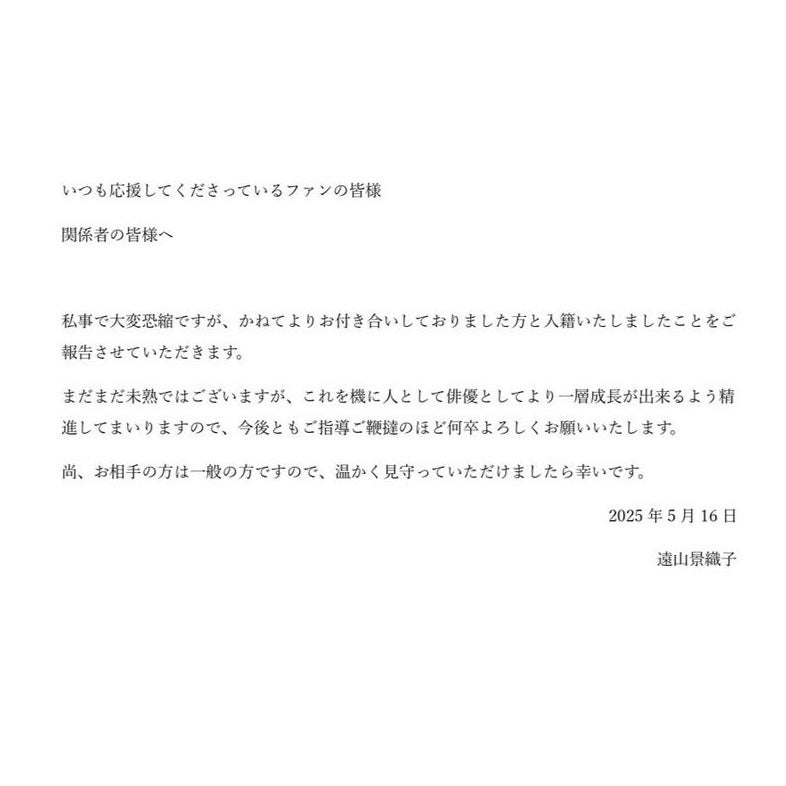今日は沢山在籍するKATO マニ50の一部を初期車番化~ちょっとした改造をやります。先日のスユニ50と全く逆をやるわけなんですがはるかに難しい、満足いく出来ではありませんが😅、思いついた工夫をやってみました。
いつもご訪問頂きありがとうございます。以下本編です↓。
少しづつ増えて9両在籍になっていたマニ50、全てKATO 5140相当(一部セット由来品を含む)です。左2両がちょっと手を加えた初期車番になります。全て荷物列車への連結設定、編成中間が多いので締切扱、室内灯を消灯している車両が多いです。
1両だけ5140単品オリジナル車番で残った・マニ50 2191以外は全て改番車になりますが、KATO製品は左端のドア窓が下降式の後期車で再現されているところにミソがあります😅。
改番した車両には初期車番が混ざっているんですが、こちらは左右どちらもHゴムドア窓だったらしい..初期形を後期車番に改造したスユニ50と全く逆😅~手前の車両など9両中2両を両端Hゴムに改造したのが主な内容です。以下リンク記事↓に書いたのと同じ鉄道ファン誌から知恵が付いた”知らぬが仏”パターンです😲。
Hゴムを入れてみました。作業的には大したvolumeではありませんが、ちょっと歪んだりイマイチ..下辺のつなぎ目も気になりますが、↑リンクのスユニ50のようにあったものを削るより、無かったものを自分で作る方がはるかに難易度が高いです😲。
Hゴムの素材として買ったのがこれ、ケンタカラーワイヤー#32;実測0.23mmのホワイトです。実製品は白からグレーと書かれていたので無塗装で使えるだろうとポチってみました。ビーズフラワーショップさんで注文したのでオシャレな包装で届きましたが..まさか鉄道模型のHゴムに化けるとは思われていないでしょうね~😁。黒の#32は手持ちがあってテスト製作したんですが、自分で塗装したグレーが剥げ易かったりしたので買ってみました。
↑のリンク記事で余ったスユニ50の窓ガラスを切出し、周囲に添わせることで形を出しました。四隅がラウンドコーナーになり過ぎるのでこの後精密ピンセット等を使っての補正がかかります。ドンピシャの位置で切断するのも難しいです。
作ったものを少量のゴム系接着剤で貼付ける という方法です。若干歪みはありますがHゴム表現はいくらか出っ張らないと様にならないと思ったのでこんな方法でやってみました。もうちょい細くても..とも思いますが私の知る限り最細の商品を入手しています。写真は盛アオ車(大荷2運用の印刷は何とかしなきゃ なんですがまだ手が付いていません😅)、
・マニ50 2056です。’80年頃の盛アオには初期車番しか在籍していなかったらしいのでこうなりました😁。
もう1両・マニ50 2068も同様、南トメも初期車番在籍だったようです。今回改番した訳じゃなくて、元々この車番だったけどスタイルは後期車番で走ってた😅、です。
もう1つ、製品の後期車番は写真の前位側台車に車軸発電機が付いていましたが
初期形は後位側だったとのことなのでこれも再現、前後の台車を交換しているだけです😁。(1枚上とボディー逆向き撮影です。窓配置が違いますよね。)
マニ50の前期0番台(2001~2072;全車電暖車なので2000が足されます。)はブレーキシリンダーが台車架装、後期100番台は車体床下と違いがあったようですが、後期車番のKATO製品の矢印付近にある筈のブレーキシリンダー表現は見当たりません。台車架装も台車内部で外見上の差は無かったようなので、ここは追及しないことにしましょう😅。
線路常設の初期形マニ50はED75 1014牽引、東北本線急荷1031レ編成に連結です。横浜羽沢発青森行の列車ですが、首都圏をスルーして運用された車両が多いちょっと珍しい列車でした。
3両連続の最後尾;7両目が・マニ50 2056 盛アオです。僅かな違いですし納得できる出来では無いですが初期形マニ50、ちょこっとアクセントになるかな~😁。カラーワイヤー以上に上手くやれる方法があれば試してみたいとは思いますが、今はこれで精一杯かな~?と思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。