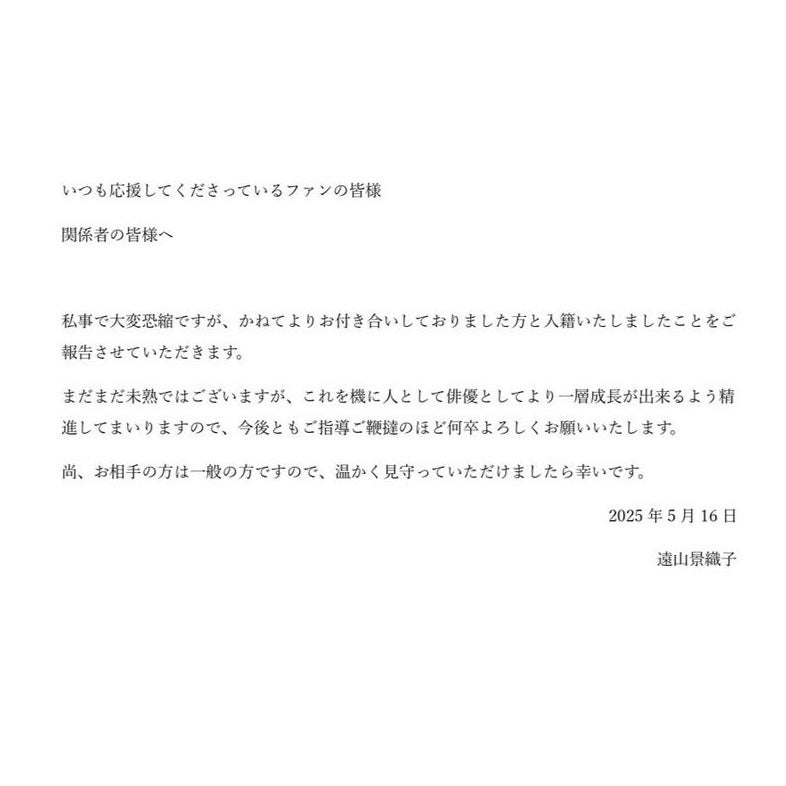今日はDCC車両検知化をやっているローカル駅付近ですが、その前に..必要になったあちこち手直しの話です。電灯を入れた跨線橋を追加しています。
いつもご訪問頂きありがとうございます。以下本編です↓。
唯一ジオラマ的?風景表現を入れているローカル駅周辺です。配線工事の為一度バラシているのであちこちヒビが入ったりしています😅。単線区間で私の所では唯一の交換駅、これまで車両検知化した区間は複線がメインでしたから、単線/交換と先に仕上がったリバース↓で自動運転や信号の動きなどどういうことになるか?試してみようとDigitrax BDL168によるDCC車両検知化を行いました。(手前は自作のカンテラ尾灯を付けたKATOタキ35000です。)
写真奥の方に実際点灯する信号機の敷設テストをするにもいいかな?と思います。DCC車両検知=どこに列車が居るか分かりますから、走行区間に応じて信号機を作動させることが出来ます。PC画面上のvirtual信号機は作っていますがそれだけでは物足りない😁、しかし信号システムがまた高価みたいなんですよね~😅。ローカル駅周辺なら少ない本数でどんなものか?を試せるというのもありました。
車両検知化する区間はポイントデコーダ(上に写るDS51K1)の駆動電源を線路から貰っていると、列車が居なくても在線表示(常にデコーダが電流を喰っているから)になってしまうので、デコーダを撤去して外部配線化します。
矢印に外部配線のケーブルが覗き見える😅、手直しが必要ですが信号機が稼働してからになるかな~。(信号システムはまだ購入もしていません😲。)
DCC関連の話はまた改めて書くとして、今回はローカル駅付近の手直し関連が中心になります。先ず対向式ホーム1,2番線間をつなぐ渡り板ですが、浮いて斜めになったりどうも扱いにくい😅..
渡り板を廃止することにしました。幸い写真下方;柵付のホームエンドが手持ちにあったのでこちらに交換します。KATO 23-241 小形駅舎セットに入っていて使っていなかったものです。
ローカル駅とはいえ、1階層留置列車の出入庫線を兼ねていますから、ロング編成が頻繁に通ります。写真はED75 1001+ED75 1017+24系12連寝台特急”ゆうづる”通過シーン..😁。
長大編成がどんどん通過するのに渡り板はちょっと..というのもありました😅。そうなると右に写る跨線橋が必要になります。
KATO 23-224;イージーキットの跨線橋を買って組み立てました。数か月前の購入;組んで置いただけの姿が最近の記事に写っていたかも知れませんが😅、
今回は片側をホームに固定し、照明を入れています。詳しくは書きませんが矢印のように極細テープLEDを貼付け、階段も同様です。左だけホームに固定したのは給電ケーブルを通すため、ホーム下に2本ニョキっと生えるのが集電板になります。右に写る屋根は下からビス止め固定する構造でしたが、それをやるとテープLEDを仕込めないので仕方がない..ゴム系接着剤固定としました😅。(矢印が無くなっていたので写真を差し替えました)
ホーム照明を入れていますから跨線橋が真っ暗じゃおかしいですよね😅。丁度2番線(左)の給電端子が近くにあったので、上述集電板を接触させて通電します。最初煌々状態だったので抵抗を付けて減光、ホームより少し暗いイメージとしてみました。右にチラッと写るのが上述23-241の小形駅舎、駅舎内は電球色照明としています。
手を突込み難い場所で細かい作業をやってて、ホームの柵を折っちゃいました😅。
補修します。縦方向に穴をあけてカラーワイヤーを通し、柵と固定用の突起を連結します。瞬間接着剤を入れて固定、これを何カ所もやりました。折れちゃった貨車のブレーキハンドル補修と同じやり方です↓😁。
車両検知の配線工事と同時にあれこれ手入れすることになりましたが、奥に見える跨線橋~思ったよりいい雰囲気かも😁。DCC関連についてはまた改めて書こうと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。