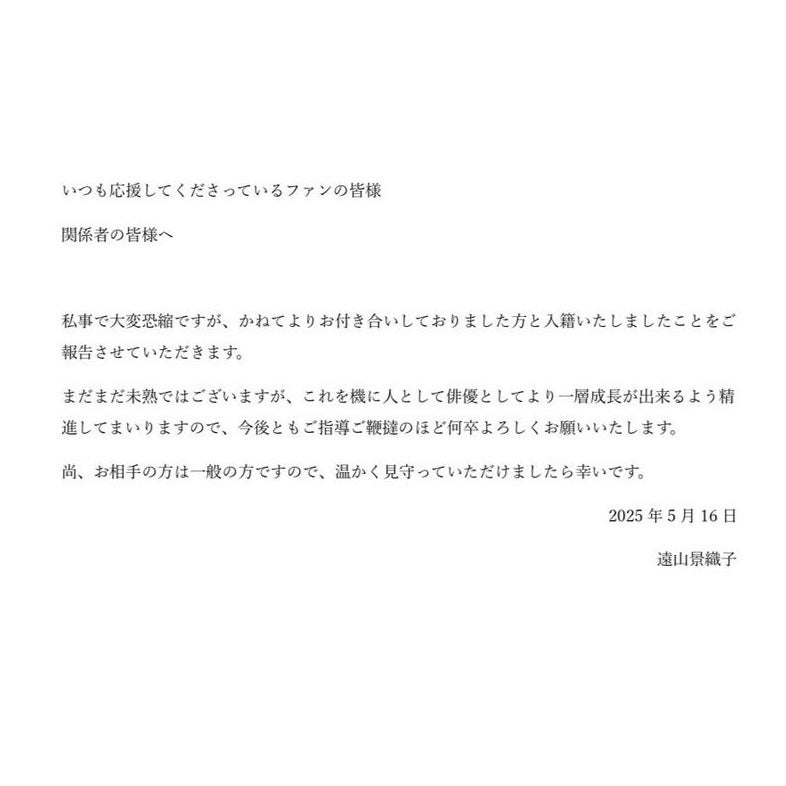今日はKATOから発売された近鉄ビスタカー10100系です。お約束の自作室内灯仕込み作業なんですが集電部が目立たないように工夫~色々あったので今回は先頭車編 です。(比較のためKATO純正室内灯を入れようとするも上手く行かなかった..😅という話も出て来ます。)
いつもご訪問頂きありがとうございます。以下本編です↓。
近鉄ビスタカー10100系(KATO 10-1911 3重連セット)です。構造面で色々工夫がみられる楽しい製品↓、今回自己流の室内灯が入りました。手前がC編成のモ10118、奥がA編成モ10105です。色々あって記事数が多くなりそうなので、頻度を上げてUpしていきたいと思います😁。
さて、先頭車の室内灯施工にあたり考えたのは...この車両全長に渡り窓だらけ😅、普通にやると集電部が目立っちゃいます。右端は連接台車の可動部があって集電を入れるのが難しそうだったので、製品設定と同じく運転席後ろ付近を使います。
自作との比較のためKATO純正室内灯(LED室内灯クリア)を入れてみようとしたんですが、どうにも上手く行きませんでした😞。矢印;枠を外したLEDユニットを屋根裏に仕込み、ズレないようにボディーを逆さにしたまま床下を組み込むように書かれていましたが、先頭車は(私の把握した限り)ユニットの固定要素が無く組込時にズレちゃいます😲。比較の為なのでこれ以上突っ込みませんでしたが、屋根裏の突起位置、形状がちょっと違えば楽に付けられるんじゃないかな~?😅。何とか組めたとして折曲げた集電板とLEDユニットから斜めに伸びるピンが接触する構造、乗降ドアと窓1枚目から室内灯集電部がモロ見えと思われます😅。
私がやった自作室内灯は例によりテープLED(120LED/mタイプ)を屋根-ボディー間挟み込み、左側にブリッジダイオードと抵抗、集電銅板を付けています。床下機器側からはリード線が上へ向けて突き出し、集電銅板に接触して室内灯に給電します。
KATOの集電板の先を切断して余った抵抗のリード線をハンダ付けしたもの、製品と同じく矢印に挿し込む方式です。すぐ下にライト制御DCCデコーダが入っているので何となく怖いんですが😅大丈夫そうです。
電動車もトレーラーも緑線より左側は同じ構造なので、同じ方式で行けます😁。
矢印が運転台と乗降ドアの間、デッドスペースはここしか無いと思いリード線を配置しました。2枚目の写真;ドアと窓1枚目付近がスッキリなのはこのためですが、真上に集電部とブリッジダイオード等があるので付近が暗くなるのは今の所やむを得ずです。KATO純正も同位置にLEDユニットなので似たり寄ったりでしょう😅。
銅板では無くリード線を使ったのは運転席後ろの窓を極力塞ぎたくなかったからです。写真の切妻車は前面窓に合わせて右、中央の仕切り窓が縦長になっています。前面展望を楽しめたんでしょうか?
細いリード線にすることで前方から見ても出来るだけスッキリ見せるように でした。リード線が全く見えないように~の調整は難しそうですが..😅。(ジャンパ栓表現はまだ入れていません。この後考えます。)
100mmのテープLEDは入らなかったので、25mm単位で切断できる120LED/mタイプを使用、75mm長としました。白色天井板(裏)に青い線が入っていますが、テープLEDは白色ながら若干暖色系要素があるので、寒色系に調整するためです。
横から見て集電部がどこにあるか分からない~スッキリ仕上げられたと思います😁。
最初のリンク記事に書いたように、製品の電動車はライト制御FL-12、モーター制御EM-13;2枚のDCCデコーダが1両に入る構造なので、右側の片台車駆動、トラクションタイヤ2輪です。

C編成と、動力を持たないB編成の併結運転テストをやっておきました。
(行先表示についてはまだテスト段階なのであまり深く考えていません😅。)
1台車駆動の6両編成ですが登坂能力に問題無し、私の所では最急の35‰も難なく走行しました。逆にA+C+Bの9両運転をする場合に踏ん張りが効きすぎ?、2動力台車の微妙な歩調乱れを拾って?脱線が多い傾向がみられていますので何か考えます。2両目にボンヤリ見えているビスタカー;2階建中間車も既に室内灯が入っているんですが、長くなるので別途書きたいと思います。室内灯以外にもやることは色々ありそうで、工夫の詰まったいい出来と思いますし暫く楽しめそうです😁。
最後までご覧いただきありがとうございました。