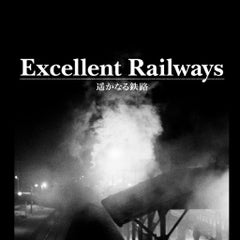案の定というかやはりというか、根室本線富良野・新得間が廃止されてすぐに(正確にはその前日あたりから)それまで公開されていなかった撮影地で撮られた写真がSNS、特にX(旧Twitter)に次々と出てくるようになった。それらの写真を見ていて感じたことを言わせてもらう。
根室本線に限らず、撮り鉄の内輪であまり知られていない撮影ポイントを無闇矢鱈にオープンにしたくないという気持ちはわかる。公開された写真を見て、我も我もと当該ポイントに撮り鉄が押しかけ、撮り鉄同士、あるいは地元との間で様々なトラブルが発生し、挙句に立入禁止となってしまうということがこれまでも度々あったことを考えると、そのような事態を避けたいと考えるのは自然である。
しかし、僕が言いたいのはそういうことではなく、そのようなタイミングで世に出された写真の受け止めである。秘匿してきた撮影ポイントで撮られただけのことはあって、どれも写真の出来栄えは素晴らしい。文句なく素晴らしい。でも、それはなんだかんだいっても過去の写真である。もちろん写真というのは撮られたその瞬間から須く過去の出来事ということになるのだが、営業列車が走っているときの写真には現役感がある。これに対し、営業列車が走らなくなった後の写真は、なんというか、言い方が難しいのだけれども、売れ残りの商品のようになってしまい、新鮮味が感じられないのだ。廃止されてから20年、30年経った写真だと、そこには「時」という付加価値が加わってビンテージものになるのだが、廃止直後の写真にはそれがなく、どうにも中途半端というか、旬を外したようにしか見えない。
青井は悔しいからそんなことを言うのだろうと批判する向きもあるかもしれない。しかし、自分の気力体力や獣害リスク等を考えると、たとえ場所を知ったとしても僕が訪れることはないだろう。
かつては、そういった未知の写真を出すか出さないかの判断は鉄道趣味誌が担っていた。というより、むしろ積極的に出していたように思う。それが廃れ、個々人がSNSで発表するようになり、未知の撮影ポイントは列車や路線がなくなるまで発表しないという暗黙のルールが形作られるようになった。その背景には、鉄道写真撮影のハードルが下がり、沿線に繰り出す撮り鉄が増え、中には屑鉄が少なからず含まれるということがあるのではないかと思う。鉄チャン人口が増えるのはある意味喜ばしいことではあるのだが、他方でこのような事態が避けようもなくなってしまうのもまた現実である。まことに悩ましい限りである。自分はいつまで鉄チャンを続けられるのかなぁと懐疑的に思うのは、こういうことを考えるときである。老兵は消え去るのみなのか。悲しいことではある。
↓蒸機が現役で走っていた頃、撮影地では見知らぬファン同士で機関車運用や撮影ポイントの情報交換が行われていた。下の2点の写真も撮影地で一緒になった同業者から教えられたポイントで撮影した。当時このポイントは趣味誌で紹介されたことはなく、ファンの間の口コミで知られるようになった。このときこの場所には数十人の同好の士が集まっていたように思う。(石北本線美幌ー緋牛内にて1975年3月)