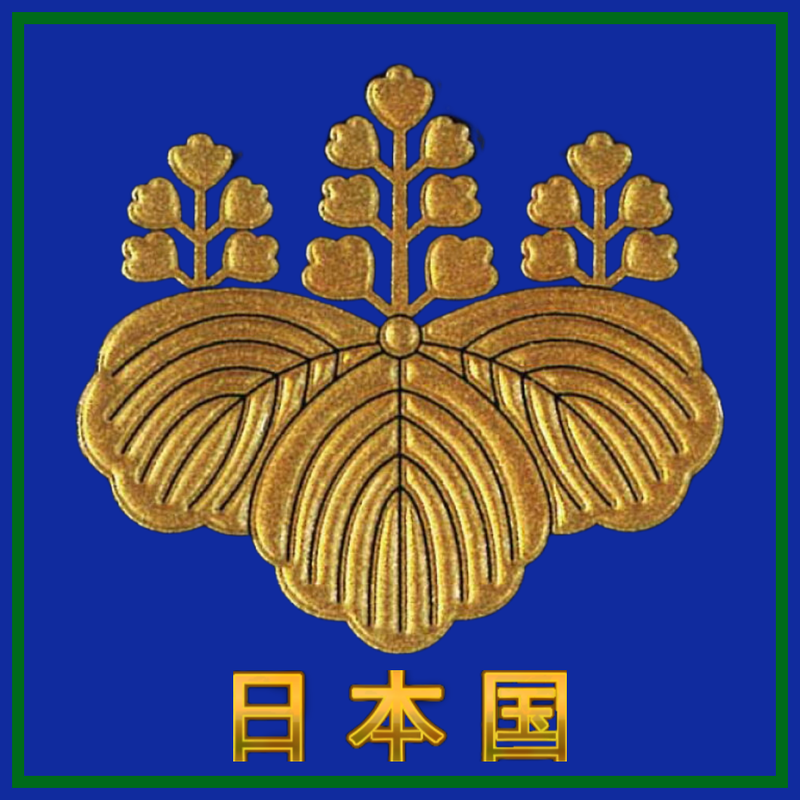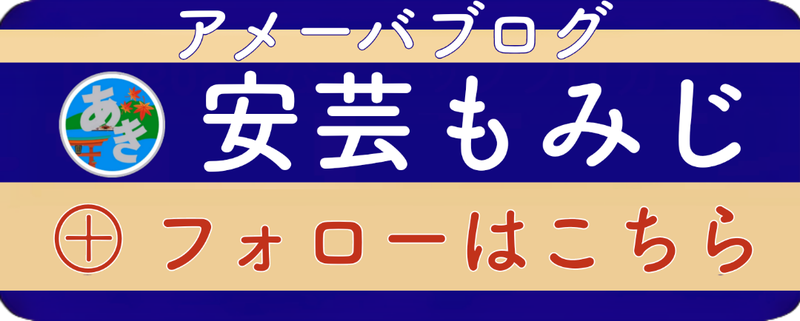安芸もみじ ─ Photographs, Historys, Railways,-JAPAN┃広島
広島発信のブログです。 基本的に「被爆2世が語る平和記念日と世界史」のためのブログなのですが、それでは年に数日の更新に陥ってしまうので。 日頃は鉄道や日記で雑談をUPしつつ、気分がノッてる日には郷土史や歴史関係をユルく語っています。---安芸もみじ⛩️広島
ブログ内検索
プロフィール
テーマ
最新の記事
カレンダー
ブックマーク
月別
2024年02月01日(木) 22時00分00秒
芸備線と持続不能の日本・その19
テーマ:機動車•DC・HV etc.広島駅で撮影したキハ40系(ラスト3枚は新山口駅)を見ながら、久しぶりに少し語ってみたいと思います。
尚、-芸備線と維持困難路線-のタイトルは″その20″からはー芸備線と持続不能の日本ーに変更となります。
1~19の内、タイトルの変更が相当ではない記事を除いて、既にー芸備線と持続不能の日本ーへと変更しました。
また、今後の更新についてはテーマが「機動車」から「日本史」へと変わります。
テーマについては「その17・備後庄原駅 / マイレールを守る旗印の駅」で、1度だけ″JNR•JRの車両じゃないいろいろ″で更新したことがあります。
また、通しナンバーは継続します。
″その18″から更新の期間が開いたのは、1つは昨年の心臓カテーテル治療の影響もあったのですけど、それと同時に記事の方向性からいろいろ勉強をし直した結果、思うところもあって止めていました。
再開につき、鉄道記事ではなくなりますが、さまざまな社会情勢を反映させた内容となる読み物になるよう、頑張ってみたいと思います。
それと、旧シリーズ名だったー芸備線と維持困難路線ーは、今回の″その19″までサブタイトルとして、冒頭へ記します。
と言うことで今回の話題は、特定技能制度4分野追加についてです。
政府が、外国人労働者を中期的に受け入れる特定技能制度の対象に、自動車運送、鉄道、林業、木材産業の4分野を今年度中の追加を視野に関係省庁が協議しているそうです。
この制度は2019(平成31)年に創設されましたが、追加は初めての事例となり、昨年には労働力不足に対応するため、永住も可能な特定技能2号の対象分野を1号にほぼ揃えていました。
そしてこの度、即戦力人材として最長5年滞在できる特定技能1号の対象分野が、現在の12分野から16分野になる••••••••としています。
ただでさえ深刻な人口減少から労働力が必要定員を大幅に下回る″2024年問題″の渦中に飛び込む今年、4月からは物流運転手の残業時間上限が規制されることで人手不足が深刻化し、輸送能力が下がり物流が停滞します。
この2024年問題の懸念を解消につなげる狙いを前提に、自動車運送におけるバスやタクシートラックの運転手などを対象分野追加することで、外国人の受け入れ枠組みが大きく広がり、日本の物流を滞らせない思惑があります。
このほか、既にある産業機械など製造分野に、繊維や印刷といった業務を加えることも検討していると同時に、鉄道でも特定技能制度を活用した外国人労働者の雇用が可能となり、車両製造や運転士・駅員などの業務を加えたいとの業界からの要望に応える予定です。
出入国在留管理庁によれば、2023(令和5)年11月末時点での数字ですが、1号は約20万人と2号は29人が就労中で、この拡大策で政府は創設時の「24年3月までに最大34万5,150人」を達成させる見込み。
建設、造船・船用工業、ビルクリーニング、産業機械などの製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品の製造業、外食業、介護に、自動車運送、鉄道、林業、木材産業の4分野が加わることとなります。
尚、介護については1号のみとなっています。
外国人材の受け入れを巡っては、政府が今国会で、現在人権侵害などの問題が指摘される技能実習制度を廃止し、新制度を創設する関連法の提出を予定しています。
広島市~新見市をつなぐ芸備線の内、最閑散区ではあるものの、利益向上よりも廃線を強行したいJR西日本の本音を探る際に、路線維持の経費と人員不足が推測の最上位となりました。
その際に鉄道への外国人労働者雇用は、なぜ認められないのか?との疑問に、生活習慣や文化による価値観の相違が安全性に影響を与えるとの懸念はあったようです。
しかし鉄道事業者としては特定技能制度の導入を希望していたようで、現場と制度の狭間で思案していた人たちを、政府の意向で導入へと傾いたようです。
その裏には、2024年問題で最初にぶち当たる物流ドライバーの問題があり、バスやタクシーの運転手への適用拡大で、鉄道はダメとする理論が成り立たなくなった故でもあります。
そして話しは変わるのですが、広島電鉄は今月1日から、路線バス 阿戸線(広島市安芸区~広島県熊野町)で、開発中の新乗車券システム″モビリーデイズ″の実証実験を開始しました。
モビリデイズはパスピーに変わる新システムですが、ここで取り上げるのは区間に応じた運賃割引のテストについて。
朝夕に阿戸学校~広電熊野営業所、昼に阿戸学校~萩原下~フジ熊野店の区間を運行する朝日交通バスにて。
そして割引対象者は安芸区か熊野町に住民票がある人で、事前に希望者が登録したICカードで乗車すると、対象区間の運賃が半額になるというもの。
利用率が年々減少している住宅路線において、住民とエリア外の運賃を区分けすることや、利用しやすい料金設定など、利用率の変動にどのような影響があるかを調査します。
芸備線は再構築委員会の立ち上げで、路線継続とその他の交通手段への転換について、これから議論は始まります。
全国統一企業体として巨大過ぎた国鉄を、地域密着と言うフレキシブル性を発揮させるために分割した民営化でしたが、それでもJRは巨大な民間企業なので、フレキシブル性の追求は難しいところもあります。
特定技能制度適用拡大がどのように働くのかも注視しなくてはいけませんが、鉄道存続またはその他の交通手段転換にしても、広島電鉄の試験ではありますが、そう言った発想の転換の導入も有効手段であろうと思います。
| ーご了承事項と免責事項ー 〇 芸備線と持続不能の日本は、第1回からの連載となっており、旧 芸備線と維持困難路線より引き継いでいます。 〇 以前の記事を前提として記述して行くので、特にスポットを当てた回でない限り、同じ解説を本文内では致しません。 〇 ローカル線が使い辛いのと鉄道の優位性が発揮できないのは鉄道会社の責任で、沿線都市へ人が訪れない原因は、受け入れ態勢が脆弱な各自治体の責任です。 〇 人口減少と山間都市の過疎化は国政の責任で、諸問題を先送りにして国鉄分割民営化を強行させたのは国民の責任です。 〇 公共交通の提供は日本国憲法と交通政策基本法に定める基本的人権の1つであり、安易に国民の権利を奪うことは許されません。 〇 街の活性化は住民と訪問者の両輪が必須で、そのためにはインフラ・ビジネス・エンターテイメントの3要素に、恒久性が欠けては成立しません。 〇 上記を基本概念として、中立的に私一個人の思いを綴っていますことを、ご理解とご了承のお願いを致します。 〇 №19までは″機動車″のテーマで投稿していましたが、№20以降は日本史のテーマへ変更します。 |