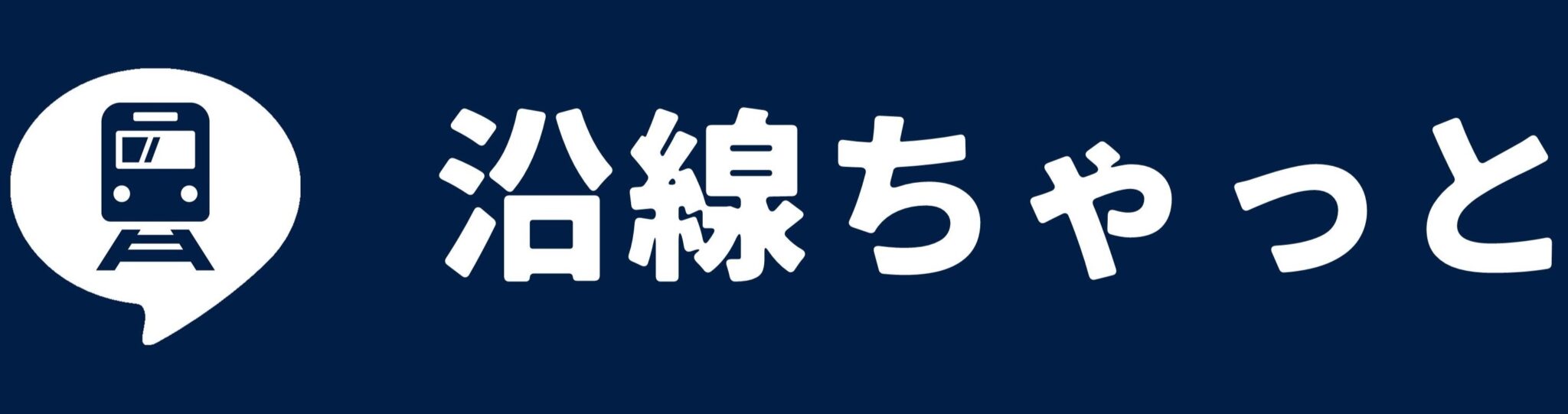こんにちは、TRAinDATAです。
今回のテーマは「所要時間」。
東京から大阪までの所要時間の変遷をグラフにしてみていきます。

まずは1889年。
新橋-神戸間が繋がり現在の東海道本線が全線開通します。
この時の新橋-神戸間の所要時間が20時間5分。東京から関西に向かうには丸一日を要していました。

32年時を進めて1921年。
当時の特急で新橋-神戸間が11時間50分で行けるようになります。
30年弱で実に約9時間もの時間を短縮できたのは凄いですね。

その9年後、時代は昭和に入ります。
特急「燕」が運行を開始し東京-大阪間が8時間20分で結ばれるようになります。当時は革新的な速度で「超特急」とも呼ばれました。

続いて1958年。
国鉄初の電車特急「こだま」がデビューしたことを受け東京-大阪間が6時間50分で行けるようになります。この頃から東京-大阪の日帰りが可能となりました。

そして1964年。
ついに東海道新幹線が東京オリンピックに合わせて開通します。1964年というと今年で開通が60周年ですね。東京-新大阪間の所要時間は4時間。驚異的なスピードです。
ちなみに翌年の1965年からはスピードアップがなされ所要時間が3時間10分に短縮されています。

時は1992年。
300系のぞみがデビュー。東京-新大阪間の所要時間は2時間30分に短縮されます。
現在でもおおよそこの所要時間ですね。

さて、今度は未来を見ていきましょう。
昨今色々と話題のリニア中央新幹線が予定通り開通した場合、2045年に品川-新大阪間が1時間7分で移動できるようになります。
156年前の1889年と比べるとおよそ20分の1。
凄まじい進歩ですね。
リニア開通へ向けての最初の課題は静岡区間の水問題です。今後の詳しい動向を追いたいところです。

まとめるとこんな感じのグラフが完成します。
いかがだったでしょうか?
鉄道高速化実現へ向けての多方面の方の努力が垣間見れた気がします。
それではまた次回お会いしましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。