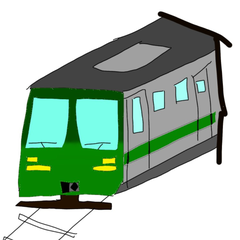まず、この記事を通して私が伝えたいことを先に言ってしまおう。
①快速の停車駅を減らせ
②京成中山駅と大佐倉駅は要らない
③京成には数字では表現できない良さがある
何故結論を先に言ってしまったのか、それは時代のせいである。私も含めてインターネットユーザーは長文を読むのが嫌いだ。書き始めたばかりなので何とも言えないが恐らくこの記事はそれなりに長くなるだろう。ろくに読まずに誤解されると京成の名誉を傷つけかねないので、このような措置を講じた。なお私の大嫌いな東武に関してはそういった気遣いをするつもりは一切ない。
総武線に対する勝ち目が見当たらない
京成線と総武線は、江戸川を越えて千葉県に入ったところから船橋駅まで、ほぼ同じルートを通っている。両者を3つの観点から比べてみよう。
①運賃
京成ユーザーとしてあまりこういうことは言いたくないのだが、京成線は総武線と比べてしまうと何もかもが劣っている。現在、総武線の初乗り運賃は京成より10円高い150円だが、来年3月から京成でもバリアフリー運賃が上乗せされるため、両者において初乗り運賃の差はなくなった。京成の運賃面での強みは、とにかく学生定期がJRよりも安いことだ。市川から八幡までそれぞれの運賃を調べてみたが、京成の学生定期は6ヶ月で7000円ちょいだったのに対し、JRは12000円である。京成の学生定期の安さには驚きだ。しかしその分通勤定期は割高である。少子高齢化により、学生の数はこれから減少していくだろう。長期的に見るとこの強みはあまり生きないだろう。
②本数
JR総武線は、津田沼までの各駅停車が日中5分間隔、津田沼~千葉が10分間隔である。快速は不規則な運転間隔であるが一応平均12分間隔である。一方の京成は、各駅停車と優等種別がそれぞれ10分間隔である。圧倒的に総武線が優位である。
③行先
総武線も京成線も通勤路線である。通勤路線の人気度というのは、ベッドタウンと都心をいかに乗り換えなしで行き来できるかで決まる。総武線は各駅停車が中央線に乗り入れており、秋葉原と新宿まで乗り換えなしで行ける。また、途中の御茶ノ水駅では同じホームで快速に乗り換えることができ、利便性が高い。総武線快速は横須賀線に乗り入れており、東京駅はもちろんのこと、新橋、品川、横浜に乗り換え無しで行くことができる。しかも総武線快速はやや本数が少ないものの、乗ってしまえば爆走してくれるので、驚くほど早く目的地に到着する。
一方の京成は、本線に乗り続けると日暮里と上野にたどり着く。押上線を介して日本橋、品川、羽田空港まで階段を使わない乗り換えで行ける。羽田空港まで面倒な乗り換えをせずに行けるのは、京成ならではの強みである。しかし言ってしまえば、羽田空港以外の目的地はほぼJR総武線に対して劣勢である。日暮里や上野は、都心へ行くための乗換駅に過ぎない。乗り換えなしで都心に行ける総武線との差は歴然である。
案の定JRに客を奪われている
ここで、市川駅(JR)と市川真間駅(京成)の利用者数を見てみよう。利用者数はWikipediaを参考にした。
市川駅の2022年度の乗車人員は52,412人/日である。市川真間駅の乗降人員は6,561人/日である。ここで注意したいのは、JR市川駅は乗車人員が示されているのに対し、市川真間駅は乗降人員が示されている点だ。乗車人員は降車客を含んでいないが、乗降人員は降車客も含む。市川駅の乗降人員は少なくとも10万人を超えていると予想できる。市川真間駅の目の前に住んでいる人も、少し歩いて市川駅を使っているに違いない。
JRと京成の駅が近い場所としては、他に下総中山駅と京成中山駅がある。何回か両駅間を歩いてみたが、市川駅と同様、京成側のがあまりにも閑散としていた。京成中山駅はなんと構内踏切を有する駅である。利用者が少ない証拠である。
ではなぜこんなにも差が生まれてしまうのだろうか。それは、京成が都心へのアクセス路線として機能していないからである。もはやJR総武線との競争になっていない。
京成は快速の停車駅を減らせ
京成という社名からわかるとおり、京成は東京と成田を結ぶ鉄道である。つまり、京成のライバルは総武線ではなく成田線である。京成がJRに勝つために必要なことは、如何に早く成田に着ける移動手段を提供するかということだ。京成線の快速の停車駅は青砥から先が、京成高砂、京成小岩、京成八幡、東中山、京成船橋、船橋競馬場、京成津田沼で、京成津田沼から先は各駅に停車する。この停車駅から読み取れることは、京成はJR総武線を意識し、快速の停車駅を多めにすることで使いやすくしているのだ。しかし残念ながらそれは快速の価値を色褪せたものにしている。京成小岩、東中山、船橋競馬場の3駅は単独駅であるが、とても快速が停まるとは思えないほど閑散とした駅である。総武線との並行区間の駅は、総武線に利用者を奪われており、利用者はほとんど残されていない。そんな駅に快速を停めるくらいなら、東京と成田の速達性を向上させた方が良い。船橋競馬場駅は京葉線の南船橋駅と近いが、総武線と同じ理由で京成の劣勢が目立つ。快速を通過させても問題はない。
駅数を減らしてダイヤの円滑化を
冒頭でも述べたが、京成中山駅と大佐倉駅の廃止を提案する。
京成中山駅は下総中山駅まで徒歩6分と近く、周辺住民の大半が下総中山駅を利用している。また、ラッシュ時間帯は普通列車の後続の特急がこの駅から隣の東中山駅手前までしばしば徐行運転をしている。京成中山駅を廃止にすれば、列車の詰まりが解消される。下総中山駅が近いから、廃止しても地域の利便性は下がらない。ちなみに市川真間駅は利用者こそ少ないが、運行上は重要な駅であり、廃止することはできない。
ここで総武線とは無縁の大佐倉駅を登場させたのには理由がある。この駅は2022年度の乗降人員が311人/日である。乗車客と降車客を合わせた数字であるから、利用者数はおよそ150人/日である。行ったことがある方ならわかると思うが、大佐倉駅は他の京成の駅とは次元が違う。いわゆる秘境駅である。東京と成田を結ぶ鉄道が持つべき駅ではない。廃止して少しでも速達性を向上させるべきである。
数字では評価できない良さを忘れたくない
ここまでボロクソ言ってきたが私は京成が好きだ。好きだからこそ無駄を省いて、少しでもJRに勝ってほしいという思いがある。その思いを記事にした。
最後の章では私が京成を好きである理由を紹介する。
①車両のバリエーションが豊富で、乗るのが楽しみ!
京成には現在、3000形、3100形、3400形、3500形、3600形、3700形、AE形の7形式が存在する。さらに3700形には2種類の顔がいる。さらに京成には都営、京急、北総、千葉ニュータウン鉄道、芝山鉄道の車両も乗り入れてくる。これは楽しくないはずがない。
②楽しいイベントがもりだくさん
京成では、カードラリーやスタンプラリーなど、楽しいイベントが定期的に開催されている。私も何度か参加したが、とても良い思い出となった。
③コスパ最強きっぷ
京成線各駅と京成成田駅をお得に往復できる「成田開運きっぷ」と、京成線都内エリアが乗り放題の「下町日和きっぷ」が通年発売されている。下町日和きっぷは、柴又、上野動物園、東京スカイツリーを510円でハシゴ旅できる非常にコスパの良いきっぷである。
これらのきっぷを上手く使い、旅を楽しんでほしい。