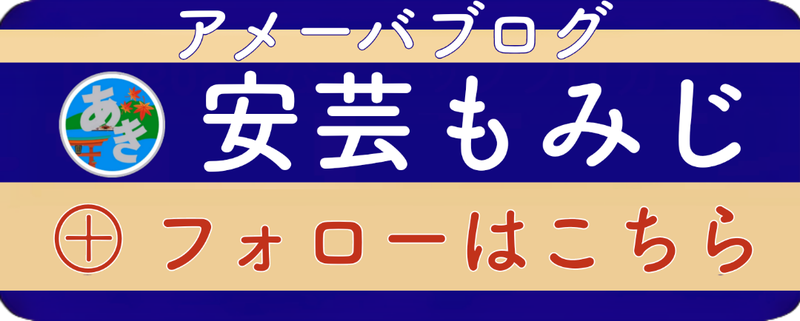安芸もみじ ─ Photographs, Historys, Railways,-JAPAN┃広島
広島発信のブログです。 2月5日発表の不具合報告がまだ復旧していないため、Xを埋め込んだ記事が端末により、途中までしか表示されない場合があるようです。 ---安芸もみじ⛩️広島
ブログ内検索
プロフィール
テーマ
最新の記事
カレンダー
ブックマーク
月別
2023年12月14日(木) 22時00分00秒
最後の長距離特急 / 681系と683系
テーマ:JR 特急形 電車•気動車

JRグループの車両形式は国鉄時代から形式称号を引き継ぐものが多いです。
例えば電車の3ケタの数字は、百の位については1~3が直流電源、4~6が交直3電源、7~は交流電源の車両と言う意味。
十の位は使用目的別表記で、0~4は通勤形もしくは近郊形、5~7は中長距離用もしくは急行形、8は特急用、9は試作車や事業要の車両と言う意味。
一の位はバージョン••••••••と認識して良いのですけど、国鉄時代はもう少し細かく区分していたり、国鉄初期は曖昧だったりしていました。
大阪から北陸の都市を結ぶ681系や683系は、文字通り直流区間から交流区間へと直通する、8の示す特急電車です。
まだ国鉄形特急電車の485系が現役だった頃、大阪から新潟への特急雷鳥や、大阪から青森への特急白鳥など、長距離輸送を担っていました。
JRグループ誕生後もそれら長距離特急列車は運行されていましたが、車両が老朽化するに伴い新性車を投入するに従い、他社への乗り入れとなる新潟行きや青森行きは廃止されていきました。
それでもJR西日本にとって8が付与される特急型車両として、関西と北陸を結ぶために走り続けてきた681系 683系。
来年3月に北陸新幹線が敦賀まで延伸して来ると、もう8の王道を往く車両は不要となります。
敦賀~大阪を結ぶ新幹線リレーとしての役目はまだあるものの、近い将来には北陸新幹線も関西圏まで延伸されるので、言わば今が最後の活躍とも。
撮影場所は湖西線ですが、かつては北陸本線しか無かった日本海方面への路線も、西日本からの短絡バイパス線として、1974(昭和49)年7月20日に開業しました。
来年は湖西線開業50周年ですが、そのキリの良い年に″特急街道″の呼称を、返上することになりそうです。
少し出すのに遅くなりましたが、10月に運転されたサロンカーなにわ 金沢の旅号の時に撮影した、北陸特急の晩年に相当するであろう姿です。
今年9月、JR東日本とJR西日本発表した北陸新幹線 金沢~敦賀間延伸開業に伴う、運行計画の概要の中で、特急サンダーバード・特急しらさぎは運転区間を短縮して存続されます。
特急しらさぎは敦賀~米原・名古屋間、特急サンダーバードは敦賀~大阪間の運転で、列車名こそ存続するものの、事実上の新幹線リレーです。
特急サンダーバードは25往復、特急しらさぎは名古屋発着8往復、米原発着7往復の運転を計画しており、全列車が敦賀駅で北陸新幹線つるぎと接続します。
観光協会や沿線自治体が切望した、和倉温泉への特急サンダーバード直通運転や、米原~金沢間の早朝便と深夜便の特急しらさぎ上下各1本について、国とJR西日本は存続を拒否し全区間運転終了となります。
早朝・深夜上下各1本の特急しらさぎは、新幹線開業後にはその時間帯の設定が無いため、ビジネス関連輸送の足を確保したかった自治体としては、複雑な心境のようです。
国鉄時代の東北新幹線のような地元経済に帰依も貢献もしない、強硬姿勢の国と民営鉄道のJR西日本の姿勢には疑問も感じますが、新幹線開業と言う経済効果は、それをも上回る威力を発揮するので、結果的に盲目化して先送り事案となることになります。
と言うことで、JRグループとしては新幹線と在来線特急の乗り継ぎ割引の全廃も控えており、北陸新幹線と北陸特急の直通運転運賃は設定されないので、新幹線リレーとは呼ばない短距離特急列車としての存続でもあります。
経営努力をしないで廃線ありきで国へ奏上するJR西日本の、そして社長は経営責任は取らないで良いJR西日本の、その体質が垣間見える北陸新幹線延伸開業に感じます。