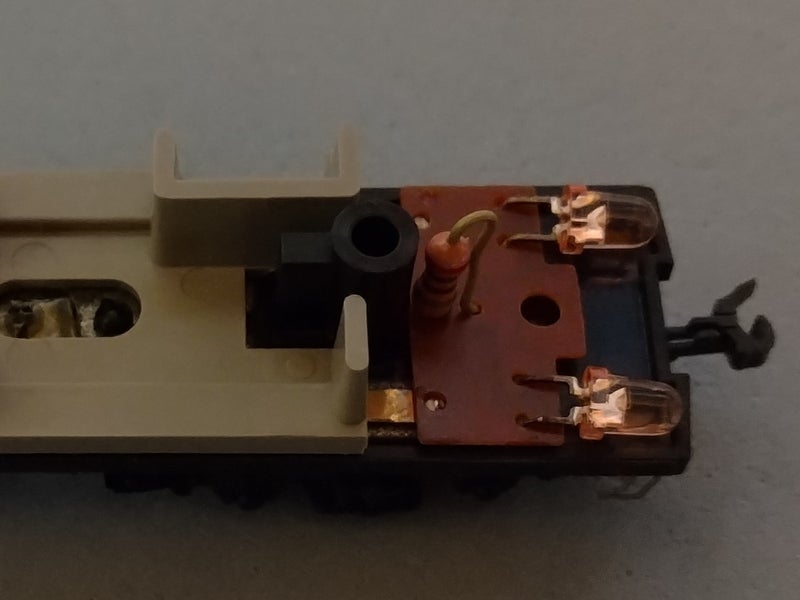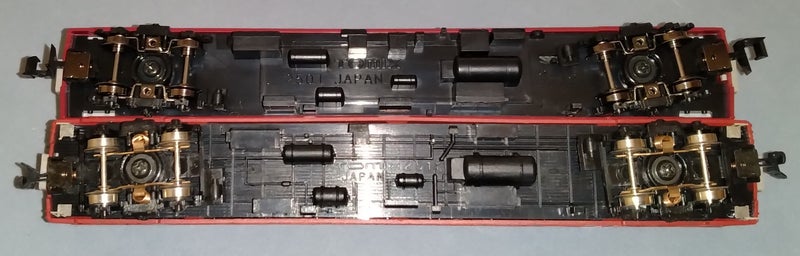TOMIXの50系は古い製品で何度かのバージョンアップと大幅なリニューアルを経て現行製品となっています。
最初期の製品は1980年ですから、もう40年以上も前になってしまいました。
いちばん最初の製品は明るい赤色で赤2号と言うよりは朱色に近いような色でした。
同時に発売されたEF71も同じように朱色っぽい色でしたが当時の赤2号の解釈って?でした。
そして、何度目かの再生産(2度目の生産かも?)で正しい赤2号で発売されましたが品番等は変更なく。
TOMIX オハフ50(品番:2511)
この車両は品番こそ2511ですが、かなり手を入れています。
・車番は印刷済み ⇒ オハフ50 21を オハフ50 2487にインレタで変更。
・ベンチレータは屋根一体成型 ⇒ ベンチレータを別パーツ化。
・テールライト非点灯 ⇒ 片側のみテールライト点灯化。
・サッシ以外色なし ⇒ Hゴム部分に色入れ。
・JRマークなし ⇒ JRマークインレタを貼り付け。
・プラ車輪 ⇒ 金属車輪化。
・室内灯なし ⇒ 純正品の室内灯を取り付け。
・乗務員ステップなし ⇒ 銀河モデルのパーツを取り付け。
・アーノルドカプラー ⇒ KATOカプラー化。
・幌枠 ⇒ 製品についていた小型のものから現行品のパーツに変更。
ですので原型とは言えいぐらい弄りまくってます。
この後の製品は幌部分が改良され、TNカプラー対応の床板になり品番が変わっています。
TOMIX オハフ50(品番:2501)
こちらは上のオハフ50から大幅リニューアルされた製品です。
ベンチレータも別部品になり、テールライトも点灯するようになってからの製品です。
Hゴムについても車体側での成型から、ガラス側への成型に代わっています。
こうやって見ると車掌室の窓が小さくなったような気がします。
現行の製品はこの製品がベースになっていると思われます。
(我が家にはありません)
現行品はドアレールに銀色と、方向幕のHゴムにも色が入りました。
これが値上げの口実かどうかは知りませんが、製品として良くなっているのでよしとしましょう。
これも中古(ジャンク)で購入。いつだったか忘れましたが。
上が2501のオハフ50、下が2511のオハフ50です。
古い2511のほうは所属標記(広ヒロ)と換算標記が印刷済みになっています。
新しい2501のほうはそれらの標記類は省略されてしまいいました。
どちらの製品も方向幕のHゴムは色が入っていなかったのですが、レボリューションファクトリーの50系Hゴムのインレタを転写しています。
さすがにこのHゴムにグレーを筆で入れるのは難易度が高すぎます。
現行品はこの部分も印刷済みになっているので助かります。
左:2501、右:2511です。
Hゴムの表現で随分表情が変わりますが、旧製品も悪くはないプロポーションだと思います。
2511のほうはHゴムに色入れしています。
またテールライトは点灯化していますが、本来は一体成型です。
幌はサイズが全然違う(小さいのが付いていた)ので、貫通扉上に四角い穴が開いてしまいました。
屋根はベンチレータを別部品にしただけでグッと良くなりました。
テールライトはKATOのASSAYパーツを買ってきて付けてみました。
トイレから車掌室側の室内パーツを削って強引に入れました。
床板が浮いてしまって押さえが効かないでテールライトの基盤の集電部分を挟んだうえで、両面テープで座席パーツとウェイトを貼り付けました。
パーツはKATOのオハネフ12のテールライト基盤です。
赤色LEDが2発に抵抗が基盤に対して縦に付いています。
この頃はまだ電球型のLEDが主流でチップ型のLEDはまだまだ。
テールライトのレンズはKATO113系のライトパーツからテールライトのレンズだけを接着しました。
ライトケースはプラ板で自作して光が漏れないようにし内部にアルミテープを貼り付けています。
まあ、今時こんな改造する必要もないでしょうけれど、改造したのが随分前なので何の参考にもなりません( ´∀` )
裏返しの床下機器です。
新集電方式台車になって、TNカプラー対応になったのが2501(上側)です。
ということで、実車のオハフ50です。実車と比べてTOMIXの製品はどうでしょうか。
オハフ50 2485 (仙カタ) 山形にて。
奥羽本線でまだ50系の普通列車が走っていた頃でした。
福島から板谷峠を越えてきて山形で下車後に撮影。
後ろに左沢線のキハ40がちらりと見えます。
最後までご覧いただきありがとうございました。