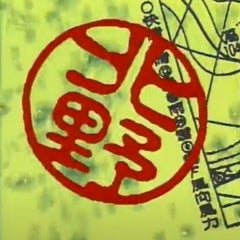相変わらず遅筆でスミマセン。
いよいよ今回から本格スタートとなる『鉄道150年記念・特急にっぽん縦断2022』の旅ですが、ようやく本篇に入り、起点の稚内駅から始まる北海道篇を紹介します。
トップ画像は鉄道150年に因んで、最初のルート・宗谷本線の筬島~佐久に設置されている同線の旭川起点150キロポストです。それでは、旅の始まり始まり~。
『日本最北の特急』
第1ランナー
宗谷本線 6064Dサロベツ4号
稚内 13:01→旭川 16:49
- 乗車距離:259.0㎞※実キロ 表定速度:68.2㎞/h)
※車両は51D宗谷の折返し。詳細は前回記事をご覧ください(札ナホ キハ261系SE-203+SE-101各編成☆①キロハ261-203※指定席区画)。
『終着駅は始発駅』という歌がある。
終着駅は旅の終わりではない。またそこから折り返す列車の始発駅でもあるのだ。
ここ、日本最北端の駅・稚内も、人生に疲れ最果てを目指した旅人が降りてゆき、そしてまた新たなスタートへ向けて奮い立つ…そんな思いを抱いて帰ってゆく、そんなシチュエーションのドラマが数えきれない程あっただろう。
その稚内だが、この日の気温は20.5℃。ほぼ平年並みといっても良いだろう。北海道が記録的猛暑を記録した昨夏に設置されたカントリーサイン入りの電光掲示板だが、『北海道&東日本パス』を利用して旭川からの普通列車で降り立った約1年前の2021年8月7日には31℃を表示(ちなみに同年7月29日には過去最高気温の32.7℃を記録)、夏でも比較的冷涼な稚内だけに、コレには流石の私も「なまらビックリ」させられた!
◆旭川起点259.4㎞の『怪』
かつては写真中央奥に見える『北防波堤ドーム』まで線路が延びていた宗谷本線だが、露スケに南樺太を奪われ稚泊航路が運航停止、その後防波堤ドームの手前まで線路は短縮された。しかし近年再開発で整備され、インターロッキング上に線路を模した石材が敷かれている事がソレを物語るだけだ。
その宗谷本線、旭川起点259.4㎞が終点という扱いになっているが、実際現在の稚内駅の線路終端部(停止目標)に設置されているキロポストはジャスト259㎞。つまり、実態とは全く乖離した状態が続いている。どうも、終端駅に関しては線路の終端部を終着点扱いにしているから…らしいが、南稚内駅が現在地に移転した1952年に改キロされて以来ずっと変わらず、線路終端部が短縮された現在もそのままになっている。もっとも、主要駅からの運賃料金がこの400mの差で変わる事がないためか、クレームを付ける者もおらず特に問題にはなっていないのだろう。尚、乗車距離はその実キロを表記し、表定速度もソレに基づいて算出させて頂いた(以降乗車する列車も、実キロが判明している路線に関しては同様の扱いとする)。
◆一路、最南端へジグザグ特急日本縦断の旅、始まる
さて私は下り宗谷号の折返し列車であるサロベツ4号(※不定期列車)を第1ランナーとし、ひたすら最南端へと目指す旅に出る。時計を見てもお判りの通り、発車時刻の約3分前に改札を抜けるが、改札口の駅員に『稚内から枕崎ゆき』の出札補充券(出補)を差し出しても特別な反応もなく…ちょっと寂しい。まぁ同じような乗車券で旅に出る乗り鉄が多いからなのか。
慌ただしく撮影を済ませて乗り込む。
かつてはキハ183系で札幌まで直通していたサロベツ号だが、5年前のダイヤ改正以来車両数削減の影響でキハ261系に置き換えられ、以来2往復が旭川発着となって4号は下り宗谷号の折返し運転となっている。しかしその4号も夜間の3号と共に閑散期運休という不定期列車になってしまった。皮肉にも、急行時代から札幌~稚内を結ぶ列車のスジは全て旭川発着となり、かつて旭川発着だったキハ54形急行『礼文』のスジ(現在の宗谷号)が札幌発着で残るという結果に落ち着いている。
本当は『はまなす編成』による運転日に乗車したかったが、日程の都合上ソレは叶わなかった。
「席の暖まるヒマもなく」(鉄道ジャーナル初代編集長・竹島紀元氏風に)第1ランナーは稚内駅を発車。今回乗車したHE-203編成(1999年製)のキハ261-203の普通車指定席区画車内はオリジナルの青いシートが7列、定員28人という小部屋だが、結局稚内からの乗客は私ともう1人、乗り鉄の若い男だけ。指定席は中間の席がマルス上でブロックされているようで、えきねっとでもシートマップからの座席予約ができなくなっていた。
◆『急行天北』の成れの果て
列車は稚内の港を左に見ながら、国道40号線の改良工事に伴い立体交差化された高架区間に入り、下りると旧国道40号線の跨線橋をくぐり、かつての稚内機関区を見ながら南稚内駅に到着する。
その南稚内駅はちょうど100年前、『元祖・稚内駅』として当時の宗谷線(今はなき天北線)の終着駅として開業した経緯を持つが、先述の通り1952年に現在地に移転されており開業当時の面影はない。実は、この旅を企画するにあたって『稚内・鉄道開通100周年』の節目の年に重なる事もあり、その記念も兼ねているのだ。枕崎ゆきの出補を当駅で購入した理由は概要篇にも述べた通りで、特急券はえきねっと予約。
その南稚内駅を出発後、かつての天北線跡が左に分かれてゆくが、廃線から33年も経ってしまった今ではその痕跡もわからなくなっている。写真に見える3階建て公営住宅の手前がかつて線路のあった地点で、その先は『天北通』という市道に改築された。
今回乗車したサロベツ4号は、かつての急行『天北』のスジだった列車。本線だった過去の面目躍如ともいうべき列車だったが、名前の通り路線と運命を共にした。天北線の廃線に際し稚内市が急行存続を強く要望したため、宗谷本線経由(急行『宗谷1・4号』、後のサロベツ号)に変更されたのである。
◆宗谷本線の絶景区間を行く
送り込みの下り宗谷と重複で恐縮だが、抜海の丘を上り、「進行方向右側に…」と車掌からの車内アナウンスが流れ、日本海に浮かぶ利尻島と礼文島が見える。曇り空というイマイチな天気ではあるが、このようにバッチリ見えるとは思わなかった。僅か10数秒と儚いが、まさに幸先の良い旅のスタートを飾る事ができた。
コチラは勇知~兜沼の牧草地の奥に見える利尻山。
白いビニールに包まれた牧草ロールが点在しているのがユニークだが、この牧草ロールはかつて牛の飼料の保存場所だったサイロに代わるモノで、ビニールの色によって日光の当たり具合が変わり、その事によって牧草の味も変わるそうだ(他には黒、白黒、緑、オレンジなどが見られる)。
ここで私は、下り宗谷号乗車前に旭川駅で途中出場して駅弁屋(旭川駅構内立売商会)で購入した『ホタテステーキ牛すき重』(¥1380)を昼食として頂く。サロベツ4号出発前に稚内駅で昼食を確保する時間はないと見て予め用意しておいて正解だった。
黒胡椒でソテーしたシンプルな味付けがホタテ本来のうまみを引き出していて、牛すき重のほうはかつて販売されていた『北海道牛すき重』と同じ具材。肉と海の幸が合体したちょっと贅沢な駅弁である。
相変わらずの曇り空ではあったが、利尻山を眺めながらの旅は続いていた。
◆早くも旅行継続の危機
しかし、直後に悲劇が訪れる。
拙ブログで紹介した乗り鉄で、何度か旅のお伴をして頂いている旭川在住のらんちゃん女史から悪夢のような知らせのメールが届いた。
「今日の北斗、軒並みダメだ~」
「えっ?」私は目を疑った。
すぐにJR北海道HPの列車運行情報を開くと、上り北斗は道南地区の大雨の影響で札幌発の16号以降の便が終日運休…。オーマイガ~![]()
『時刻表テツ』の方ならだいたい想像は付くと思うが、私は旭川に到着後、ライラック36号→北斗22号に乗り継ぎ、そして新函館北斗で下車し、1泊後翌朝の北海道新幹線はやぶさ10号で北海道から脱出する予定であった。しかし、その計画は見事に潰れる事となる。
確かに、この日の道南(渡島・檜山・胆振)は大雨の予報ではあったが、朝の運行情報を見ても計画運休の予定は入っておらず、どうにか辿り着けるモノだと信じていたが、結局はその不安が的中してしまった。むしろ、利尻山の絶景が見られた事によって運を使い果たしたのか…。
さぁ、どうする?いくら時刻表とニラメッコしても、どうにもこうにも本日中には新函館北斗には辿り着けない。いずれにしても明朝のはやぶさ10号に乗るのは不可能だ。高速バスでの移動も考えたが、そうなるとこの旅のコンセプトとは大きくかけ離れてしまう。
とりあえず、札幌まで向かい、その後の事を考えるとしよう…。意気消沈した私はぼんやりと天塩川を眺めていた。
やがて天塩川とも別れ、塩狩峠を越えて上川盆地に入り石狩川を渡るが、南下するにつれて、雲はどんどん厚みを増してゆく。終着駅(乗換駅)の旭川に着く頃には雨が降り始めていた。
◆ノーマスクブチギレ野郎
サロベツ4号は旭川駅に5番線に到着した。私が降りる支度をしていたらグリーン室から出てきた恰幅のいい男が私に対して捨て台詞を吐き、デッキ仕切りの縁を蹴って威嚇してきたのだ。
「なんだお前は ![]() !!」
!!」
何のことかわからないだろう。事の発端は、トイレへ行くためか普通車室通路を歩いていたその男がノーマスクだったのに憤慨した私は奴を睨み付け…いや、正確には「白い目で見た」というのが正しい。たまたま目が合ってしまったが、その時は何も手出しはしてこなかった。「お互い様だ!」と言われても仕方がない。旅行が予定通り進まなくて意気消沈している私に反撃する余裕はなかった。まぁ直接手出ししてくるようなら駅員もしくは鉄道警察でも呼んでいたが。
それより、この男の着ていたTシャツ…。よく見るとワクチン云々の英文が書いてある。一体何が言いたいんだ?こんな品格の欠片もない輩がグリーン車を利用していたのも含めてちゃんちゃらおかしくて!まぁヤンキー気質が抜けきれず残念な歳の取り方したオヤジなのだろう…。このような輩には何を言っても通用しないので妙に関わらないほうが身のためだ。マスク云々の話をしたらキリがないのでこの辺にしておく。
結局、初日の第1ランナーのサロベツ4号で早くもケチが付いてしまったが、気を取り直して隣の6番線に停車している3034Mライラック34号に乗り換える。

『日本最北の特急電車』
第2ランナー
函館本線 3036Mライラック36号
旭川 17:00→札幌 18:25
- 乗車距離:136.8㎞ 表定速度:96.6㎞/h)
そんなライラック号であるが、カムイ号と共に特急電車としては日本最北を走る列車だ。今や旭川特急はコチラのほうが主役になっている。今回乗車したHE-101/201編成はズバリ『ASAHIKAWA』ラッピング。789系の中でも最後に製造された車両で、青函特急としての活躍は僅か5年にしか過ぎなかった。内装も他編成が全てリニューアルされている中、オリジナルの赤と緑の平織物シートを残している。今回は諸事情で指定席ではなく⑥号車自由席に乗車した。
旭川からはずっと雨の中を走行、時折激しく降る処もあった。もう車窓どころではなく結局1枚も撮らずに意気消沈のまま札幌駅3番線に到着…。

◆苦渋の決断?
改札口のLED発車標には、特急北斗の終日運休がスクロール表示…。この日は函館本線山線も運休しており、大雨の影響は計り知れなかった。稚内からサロベツ2号で出発していれば上手く切り抜けられたためこんな事にもならなかったのだが、そのためには前泊か夜行バス(※7月から再開)に乗らねばならず、さらに日程が延びるので断念した事情がある。
結局、先へ進めないので改札口で事情を説明し、北斗22号と翌朝の新幹線はやぶさ10号の特急券を精算窓口で一旦払い戻す。乗車券も本来ならば札幌駅で途中出場できないルール(※白石接続のため)だが、特別に一度改札口を抜けても良い事になった。
西コンコースでは、鉄道開業150年に因んだパネル展を行っており(※10月16日で終了) 、せっかくなので覗いてくる事にした(前回記事のトップ画像はその展示の一部)。
全てを紹介すると長くなるので割愛するが、 展示の中には1948(昭和23)年の鉄道路線図もあった。まだ羽幌線や湧網線などが全通する前であったが、現在のスカスカになってしまった路線網から見れば私鉄も含めてかなり充実していた事が判る。
その後私は大丸のデパ地下で夕食を買い、一旦帰宅するため学園都市線2631Mに乗車、思わぬ形で旅行1日目が終了する。
初日からいきなりケチが付いてしまったため、最早旅行継続の意欲も失っていたのは事実だった。札幌駅まで乗車した分を差し引いた分乗車券は払い戻し、または稚内まで無賃送還し、送り込みで使用したLOVEパスで札幌まで戻る事もできる。とにかく、明朝から北斗が動くか動かないかによって決める事にしよう…。ただ、継続するにしても途中の行程は削らざるを得ない判断を迫られるのであった。
つづく