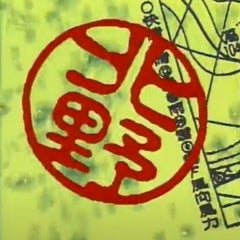本日10月14日、日本🗾の鉄道開業からついに150年の記念日を迎えました!
パチ~👏👏👏🎉🎊🎌
その節目の日に合わせまして、先日お伝えした通り8月1日から実行した『鉄道150年記念・特急にっぽん縦断』の旅を今回から順次アップ致します。
尚、拙ブログは他の話題の記事を挟む事がありますので、必ずしも本シリーズを連続でアップするとは限りませんのでご容赦願います。
北から北海道から南は九州まで、日本縦断鉄道の旅が始まるのですが、まずはスタート地点である日本最北端の駅・稚内駅まで送り込みをしなければなりません。今回はプロローグとして、その送り込み篇から紹介させて頂きます。
その8月1日、まずは最寄り駅から学園都市線522M(札サウ733系B-112+B-118)で札幌駅に向かいます。
(以下、文体が変わります)
番外ランナー(送り込み①)
札幌 6:56→旭川 8:32 71Dオホーツク1号(網走行)
編成表(太字と☆は私が実際に乗車した車両。以下同じ)
遠軽←①(指)キハ183-9560 ②(G)キロ182-505 ③(指/自)キハ182-7551 ④☆(自/指)キハ183-8563→札幌・網走
522Mが札幌駅8番線に6:38到着後、向かいにちょうど入線してきた71Dオホーツク1号に乗り換える。
「ん?稚内に向かうのにオホーツク?」…普通の方ならそう思うだろう。
送り込みはあくまでも『番外篇』扱いだが、せっかくなので『特急にっぽん縦断』として車両のバリエーションを付けるために、来年2023年春ダイヤ改正で定期運用を退く事となったキハ183系に旭川までの短い間だけ乗っておこうかと。
ただ…寄る年波には勝てず、特に今回乗車した④号車(しかもNN183系一般車最終増備の1990年製)の外被はボロボロで、2枚目からの写真でも判るように剥がれた塗装を上塗りした跡が見える。昨年の「モロに錆だらけ」という酷い状態だった時よりマシではあるが、JR北海道の期待を背負ったエースの哀れな末路を見る思いで、N183系も含めて新車時代から知る者としてはツラい。

この日はいわゆる『復刻新特急色』の車両は入っていなかったが、②号車のハイデッカーグリーン車キロ182-505のみが国鉄時代の製造(いわゆる『N183系』)。現在使用されているキロ車計5両(うち3両は機関換装車)の他、もう国鉄時代製造車はキハ182形、キハ183形のそれぞれ2両ずつ、現役なのは総計9両しかない。JR化後に製造された550番台(NN183系)ですら機関換装車も含めて既に廃車が発生しており、もう最小限の車両数で運用をこなしているという現状である。
さて、コチラはオホーツク1号発車前の札幌駅西改札口。
この日は土曜日だったため、早朝からの通勤客は少なかった。
朝食の駅弁を買い込んで乗り込む。
今回は④号車17番AB席に設定されている『かぶりつきシート』(7月1日から指定席として運用)に在り付く事ができた。この時点では④号車ならば比較的乗車近日でも席を確保する事が容易だったが、流石に引退迫る現在になると、特にオホーツク1号など昼間の便に関しては①号車も含めてみどりの窓口で『10時打ち』をしてもらわねば座席の確保は困難であり、しかも1人利用だと相席になるのは覚悟しなければならない。
せっかくのかぶりつきシートだ。勿論、後向きに座席を回転させて後方展望を楽しませて頂く。6:56、JRタワーを見ながら札幌駅を後にする。私の長い旅の第一歩が始まった。
苗穂駅付近では、この後旭川駅で乗り換える51D宗谷のキハ261系基本番台車がスタンバイ。曲面ガラスのため右側が歪んで見える。
その苗穂駅を通過し、豊平川の橋梁を渡った後のいわゆる『菊水カーブ』で、同時刻に札幌駅を発車して猛ダッシュしていた721系の特快エアポート66号に追い付く。千歳線用の線路と並行する札幌~白石(平和)の複々線区間では、函館本線の特急と快速エアポート及び特急すずらんが同時刻に発車して並走バトルを繰り広げるシーンが多く見られる。
さて、今回稚内までの送り込みとして使用した乗車券は、『HOKKAIDO LOVE!6日間周遊パス』(通称LOVEパス。幾度かの発売終了と再発売を経て、本記事執筆中のタイミングでついに『近日中の発売終了』というカウントダウンが始まった…。果たして次はあるのか?)を使用させて頂いた。札幌市内から稚内までの運賃と特急料金の合計は指定席利用で¥11090なので片道あたりの単価は割高だが、途中出場の可能性など諸事情で使用する事になったのをご了承頂きたい。また、指定席は札幌~稚内で利用する場合、特例で旭川乗換でも列車を問わず通しで発券できるため、このようにオホーツクと宗谷との組み合わせでもOKなのだ(但し本来はこの場合途中出場NGだが、フリーパス故に指定券を改札機に通さなければ何の問題もない)。
④号車はかぶりつきシート以外自由席なので、岩見沢、美唄などの区間利用が非常に多く、車掌も車内改札などの業務で大わらわ。そのためこのように車掌室ではなく、④号車後部乗務員室側でドア扱いをする事も見られる(美唄駅にて)。
ここで私は、札幌駅で予め買っておいた駅弁『北海道知床とりめし』を朝食として頂く。時間帯や曜日にもよって品揃えが異なり、肉モノの駅弁は本商品しか手にする事ができなかった。
滝川駅では、根室本線で活躍するキハ40 1749(朱色5号)・1774が留置されているのが見えた。2両とも3月ダイヤ改正までは新得~釧路で活躍しており、新年度後になって旭川に転属された車両。特に『タラコ』で親しまれている1749と1758の2両は、『最長普通列車』として滝川→釧路でかつて運転されていた2429Dに入ると大いに喜ばれたモノだ。流石に狩勝越えはできなくなってしまったが、富良野~東鹿越の廃線が決まった今、再び同区間で走る事になるとは思いもしなかった。
さて…滝川駅まで行けば自由席区画の混雑も落ち着き、だいたい50%程度の乗車率に。
この④号車キハ183-8563はオリジナルのR55系リクライニングシートを装備した車両で、隣の③号車も同じ。N183系から国鉄在来線特急に採用されたR55系(※初採用は1985年の新幹線100系)シートはその座り心地の良さにいたく感動したモノだったが、北斗向けに表地の張替えを行った以外特に整備はされていないようで、使用頻度が高いせいか背もたれの詰め物がペッタンコに潰れてしまっており、シートフレームの感触がモロに伝わるという劣化ぶり。座面の感触がまだ良いだけに惜しまれる。
深川を出て納内駅を通過した後石狩平野は尽き、1969年の複線電化によるルート変更で掘られた神居トンネル(函館本線最長の4523m)をはじめとした5つのトンネルを通過、上川盆地に入る。かつての納内~近文は石狩川に沿った神居古潭の景勝地を行く区間だったが、線形が悪くスピードアップの障害でもあり、また災害リスクとの兼ね合いから山間部をトンネルで短絡する事となった。
8:32、旭川駅5番線に到着。オホーツク1号は網走へ向けてまだまだ長い旅が続くが、私のキハ183系の旅はここまで。
番外ランナー(送り込み②)
旭川 9:00→稚内 12:41 51D宗谷(札幌発)
編成表:稚内←①(G/指)キロハ261-203 ②(指)キハ260-203 ③(指)☆キハ260-101 ④(自)キハ261-101→札幌
『特急にっぽん縦断』のスタート地点である稚内へ送り込む先兵が、28分後に発車する下り宗谷号である。同時に、第1ランナーとなる6064Dサロベツ4号の車両送り込みも兼ねているのだ。
8:58、下り宗谷号が5番線に到着。やはりLOVEパス期間からか、ホームには旅行客の姿が目立つ。お隣4番線に停車中のキハ40は、札幌駅を6:00に発車して8:53に到着した函館本線923D。
私は③号車に指定席を確保。土曜日、そしてLOVEパス効果もあってか乗車率は高めで、所々相席になっている処もあった。今回乗車したSE-101ユニット(※量産先行車のため天井板の形状や木目化粧板の柄、床の色の濃さが増備車と異なる)はキハ261系のトップナンバーで、1998年の製造から既に24年も経過しているが、同じ24年の車齢でもキハ80系のソレとは全く劣化具合が異なり、やはり技術や材質の進歩は目覚ましいモノがある。
列車は名寄を経て日進駅から先、天塩川沿いの区間を走行するが、本格的にその眺めを楽しめるのは音威子府から先の区間だ。既にお判りかと思うが、この日は天気が下り坂で、札幌からの道中はずっと曇り空で推移。
佐久で一旦天塩川から離れるが、天塩中川から先、今年3月ダイヤ改正で廃駅となった歌内との間で「ほんの僅か」だけ利尻山が見えるスポットがある。だいたい旭川起点166㎞あたりだろうか(間違っていたらスミマセン)。ちょうど、天塩川の谷間となる低い土地の先に利尻山が現れるのだ。鉄道ジャーナル2017年8月号の特集記事『根室から稚内まで800㎞各駅停車の旅 存続に揺れる北辺の本線』に掲載されたほぼ同位置で撮影された写真のキャプションには「この位置で見るのはかなりの強運といえる」と記述されており、私は本当に強運だったのか?しかし、天気は曇り空。利尻山はホントに気まぐれな山で、いくら走行区間が晴天だからといってクッキリ見えるとは限らず、山のほうが霞んでいたり曇っていたりすれば山頂まで見渡せないという事も少なくない。私は気象に詳しくないのでその辺の処は良く解らないが、風向風速や湿度、澄んだ空気など、ちょうど好条件が合致した結果なのだろうか?
歌内駅跡を通過。駅名標は枠だけになり、この時点では車掌車改造駅舎(いわゆる『ダルマ駅』)は駅名がテープで隠された状態で残されていたが、現在は撤去されて旧駅舎基礎跡も含めて整地され、かつて駅があったのを物語るのは奥に見える通信中継室の建物だけになっている。
ヨド物置の待合室で知られる糠南駅を通過後、雄大な天塩川の流れが再び線路と合流し、問平陸橋を45㎞/hの徐行で通過する。この後宗谷本線唯一の下平トンネルをくぐり雄信内駅を通過後、天塩川本流の流れから遠ざかってゆく。
再び利尻山を眺められるのは旧安牛駅跡付近からで、時々見え隠れしながら勇知駅手前までの間、車窓の友となる。
列車は日本最北端のマチ・稚内市に入った。
今年度末で同市が駅管理の終了を通告、廃駅問題が再浮上して問題となっていた抜海駅を通過。ちょうど列車を見に来た夫婦と思われる2人組の姿があった。結局地元住民の猛反対に遭い廃駅は撤回されたが、1日3往復しか列車が停車せず、集落から遠い事から地元住民が利用したくてもできないという状況では廃止やむなし…というのはわからなくもない。しかし、貴重な古い木造駅舎を残す駅である事から観光資源になっているのも確かで、市長がその価値を理解せずクラウドファンディングによる存続すら否定するのは残念な事だ。
さあ、特急宗谷の旅もいよいよクライマックス。
抜海の丘を上り、日本海に浮かぶ利尻山が見えてくる。曇り空ではあるが、文句ナシの眺めだ。
稚内市街へ入り、稚内→枕崎の縦断乗車券を購入した南稚内駅を出ると、丘の上にある稚内公園に建つ『開基百年記念塔』(1978年建設)が見えてきて終着・稚内駅に到着。夏という事もあり乗客の大半は稚内までの観光客や乗り鉄らで、途中駅での降車は少なかった。
まだ送り込みだというのに本番の如く内容を割いてしまったが、ここはゴールではない。あくまでもスタートなのだ!
ちなみにお約束のショットは撮影者が多くて今回撮影できなかった。
こうして到着した稚内駅だが、折返しの6064Dサロベツ4号までは21分しかない。駅前に出て撮影をそこそこに済ませ再び駅舎に入り、北から南へ向けての旅がいよいよ始まるのであった…。
ここまでがプロローグ。ちょっと慌ただしいですが、折返しのサロベツ4号を第1ランナーとする『鉄道150年記念・特急にっぽん縦断』の旅は次回以降に紹介します。
つづく