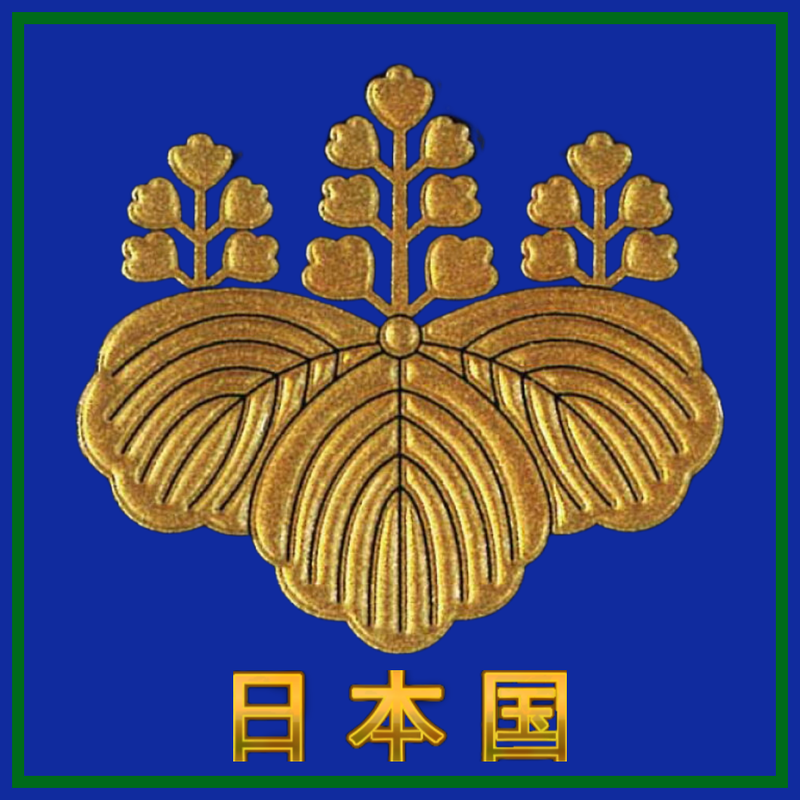
安芸もみじ./ Photographs, Historys, Railways,- Hiroshima JAPAN
お知らせ・ 2025年1月29日夕刻よりアプリにおいて、端末によってはX(旧ツイッター)を埋め込んだ記事が、途中までしか表示されないようです。 ---安芸もみじ⛩️広島
ブログ内検索
プロフィール
テーマ
最新の記事
カレンダー
ブックマーク
月別
2022年05月20日(金) 23時00分00秒
芸備線 と 持続不能の日本・その9
テーマ:機動車•DC・HV etc.今回は広島駅を出入りするキハ40系ですが、キハ120の姿も撮りました。
まずは昨日のRedWing-227系のカープ電車に続いて、カープラッピング気動車のキハ120から。
広島運転所の旧車両基地に止まっていたのを、乗っていたRedWing-227系の車内から見つけたので、スマホで慌てて撮った写真です。
さて、2020年10月22日の記事で「何をどのように実施されるのか、将来に渡り見守ってゆきたいと思います」と述べたのが、このシリーズの始まりでした。
キハ40系の記事では、芸備線を中心に赤字ローカル線問題を取り上げてきました。
あくまでも何かを活動によって主張し、未来を見据えた傾向と対策を講じるような、そんなブログにする積もりはありません。
その中でずっと避けていた話題があったのですが、主旨が趣旨なので政治的な意見などずっと避けていた話題があります。
2022年2月26日の記事では「芸備線自体が使い辛いのも、鉄道の優位性が発揮できないのもJR西日本の責任で、沿線自治体へ人が訪れない原因は、受け入れ態勢の無い各自治体の責任です」と書きました。
先月30日の記事では「中曽根康弘総理(当時)の信任選挙で、諸問題を先送りにした強行民営化に投票した全国民の責任」と言及です。
長期間に渡って少しずつ語っているので、ここで1度総括しましたが、これからの方向性として主旨を変更する積もりはありません。
芸備線を中心とした赤字ローカル線問題の記事も毎回、右往左往で支離滅裂となりそうなので、これからは″現在進行形の歴史ブログ″として展開するための統合でした。
当事者のJRとしては一刻も早く対処をという心境でしょうが、やはりそもそも論は1度通らねば、こちら協議会も行き当たりばったりとなってしまいます。
沿線住民も沿線以外の国民も得心して議論できない様に感じます。
その上で、これからどうあるべきかを構築しないと、結局は付け焼き刃な対応となり、どうしても先へ進めない赤字ローカル線問題だと思います。
そんな中で、各沿線自治体も頭を抱えているばかりではありません。
広島市と三次市では、昨2021年11月から今年3月まで販売されていた″どっちも割きっぷ″を、4月29日から再発売しました。
発売元はJR西日本と広島電鉄・備北交通で、広島駅~三次駅+三次市街地エリア間を割安で移動できる企画乗車券です。
今回はさらに乗車可能区間が追加され、芸備線の広島~三次間、高速バスの広島駅新幹線口・広島バスセンター~三次駅前間、路線バスの三次もののけミュージアム~美術館前間の3区間がセットになっています。
価格は2000円で、正規運賃の3510円より約4割引きとなっていますが、特典として広島発売分には三次市内タクシー利用券300円分、三次発売分では三次駅西駐車場割引券300円分が付いています。
販売場所は、JR広島駅新幹線口1階バスきっぷ売り場、広島電鉄広島駅営業センター、広島電鉄紙屋町定期券窓口、三次市交通観光センター交通案内窓口で、JR西日本のきっぷ売り場では取り扱いがありません。
発売期間は一旦9月30日までで、きっぷの有効期間も9月30日までとなっています。
しかし芸備線は広島~三次間の利用客は元々高かったものが、高速バスや自家用車へ転向した経緯があり、旅客をシェアすることによって輸送密度を回復させようとするものです。
芸備線の抱える深刻さは三次駅から新見駅へ向けての区間で、特に備後落合~東城間は100円の収益にかかる費用を示す営業係数が2万5416円という状況です。
その2万5416円を稼ぐには、単純なイメージとして645万9731円の経費がかかると言うことで、JR西日本は「単独での維持は困難」としています。
この単独維持困難の路線は中国地方に10路線が営業しており、特に急を要している備後庄原~備中神代間と岩徳線そして美祢線を対象に、沿線自治体へ早期解決の協議入りを要請しています。
JR西日本管内には単独維持困難路線が17路線30区間存在しており、費用負担や経営母体移管そしてバス転換など、前提無き協議をこの3路線に続いて順次求めていく予定です。
前提無きとはJR西日本として「廃線とバス転換を前提としない」との意志表示だとしていますが、このことばのイメージから沿線自治体は″存続させる″という確約が撤廃されたと受け取っています。
岩徳線ではJR西日本の担当者が岩国市で福田良彦市長に面会し「課題を共有し、地域のニーズを踏まえた議論をしたい」と求めました。
岩国市など沿線3市と山口県そしてJR西日本でつくる既存の利用促進委員会で協議することになりましたが、これからどう改善すれば良いのか議論する中で、廃線も前提に含まれるのは混乱を期すことから難色を示しています。
美祢線は美祢市など沿線3市と山口県が利用促進を話し合う協議会の会合で、JR西日本が協議を提案しました。
地元に協議を要請する中国地方の区間は、利用者数や収支率そして赤字額にはばらつきがあることから、広島支社は「区間ごとに丁寧に対応し、まずは対話の場を設けることに力を注ぐ」としています。
各沿線自治体は単独維持困難路線の発表に対しては突然のことで青天の霹靂状態でしたが、少しずつ現実を受け入れて収支報告書の発表の時には真摯に受け止めています。
線路はあって当たり前の暮らしの中で、その当たり前を守るためにはどうすれば良いかを、真剣に考えています。
鉄道は鉄道会社が運営するものですが、鉄道を利用するために必要なインフラは駅のある自治体が整備・運営するものです。
2月26日のブログで記したインフラ・ビジネス・エンターテイメントの3要素は、住民へ対してだけでなく観光誘致にとっても必須要件。
今ある駅にそれが満たせないなら、路線存続のために廃駅も必要な処置でしょう。
それは少しでも経費負担の軽減に繋がると共に、列車のスピードアップによる利用者へのサービスアップに繋がり、所要時間の短縮は利用者増加の基となります。
鉄道が利用しにくい路線は、駅へ到着してからどうして良いのか分からないインフラに問題があり、住民も旅行者も鉄道が使えないという現状です。
観光誘致や学生通学促進は大切ですが、都市そして町のシステムはどうなのかを見直す機会でもあります。
昔、三次の厳島神社へ行った時、ホスピスへ入る直前の父を連れており、三次駅から路頭に迷った体験からの感想です。
| ・ | ・ |  |
 | x |  |





















