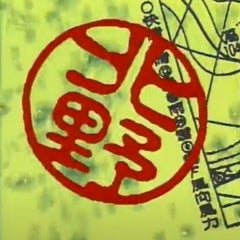相変わらず終わらないコロナ禍にも関わらず、私は6月以来コンスタントに乗り鉄しまくっていたのですが(何度も言うけど、感染予防対策を講じた上での行動です。勿論私をはじめとして、家族や周囲の人を含めて未だに誰も感染してませんよ!!)、その時の事をブログにする気力もなく…😖
しかし、今回紹介する乗り鉄は是非とも記事にせねば!と思いまして(他にもニセコ号乗車記ブログが散見されますが、「俺にも書かせろ!!」というワケで)。タイトル通り、今回は9月4日から運転開始した臨時特急ニセコの乗車記です。
何といっても、今回のニセコ号は、はまなす/ラベンダー編成の登場に伴って引退が噂されていたJR北海道のリゾート列車の最後の生き残り『ノースレインボーエクスプレス』(NRE)車両が使われるという事で、鉄道ファンからはかなり注目されていたのではないでしょうか。私も、NRE車両は昨年のフラノラベンダーエクスプレス(フララベン)運用、その後の宗谷特急代走を最後に引退か!?と思ってた位ですから…。
しかし、先述の宗谷特急代走後苗穂工場に入場し、重要部検査を受けたようで(全検ではない。ちなみに直近の全検は2016年春)外装もピカピカにリフレッシュされ、今回運転されたニセコ号で元気に復帰を果たしました!
(写真は昨年10月の苗穂工場入場時のモノ)
JR北海道最後のジョイフルトレインが再び営業運用に入るという事でファンは皆胸を撫で下ろした事でしょうが、そのニセコ号は山線区間入線、しかも久々の函館への運転という事もあってかなりの人気が予想されていたため(※一般のキハ183系3連での運転だった昨年は、HOKKAIDO LOVE!6日間周遊パスの効果もあって平日にも関わらず満席というケースも多々あった)、良い席を取るために1ヶ月前の10時打ちは必須です。勿論えきねっとサイトでの予約も可能ですが、6月27日のリニューアル(ユーザーにとってはむしろ「改悪!」)以来煩雑な操作が増えたお陰で、いわゆる『セルフ10時打ち』というのは実質不可能になってしまったため、確実に希望の席を押さえるためにはみどりの窓口に出向いて発券してもらう必要があるのです。
乗車日は、平日(木曜日)の9月9日。土日だった9月4・5日は1ヶ月前の時点から窓側席がだいぶ埋まってた状況でしたが、この9日に関しては発売初日時点ではそれ程埋まってはいませんでした。無事10時打ちにも成功し、あとは1ヶ月後の乗車を待つばかり…😊
しかし…なんかイヤ~な予感が…。
新型コロナウイルス感染者のたびたびの急増(もういい加減にしてくれよ!)に伴い、予想通りではありましたが8月27日から北海道も国の『緊急事態宣言』の対象地域に追加されてしまい、それに伴いニセコ号を含む臨時の観光列車は『花たび そうや』(※5月15日~6月6日の土日に運転予定だった)と同様に運休になってしまうのでは!?とヤキモキさせられたのは私だけではなかったハズです。毎日、JR北海道のプレスリリースが更新されていないかチェックしていました。
そして、訪れた緊急事態宣言発令の8月27日のプレスリリース…。『緊急事態宣言を受けた観光列車等の対策について』
読む限りでは、運休の文字は何一つ書いておらず、感染予防対策を講じた上で予定通り運転される事になったようです。中にはノロッコ号のように乗車証明書の配布が中止されるといった残念な事もありましたが、無事運転されるだけでも有難いと思ってたほうが良いでしょう。『花たび そうや』の2年連続運休には非常にガッカリさせられましたが、それによって落胆させられた人の気持ちを代弁するかのように記したブログ『もういい加減にしてくれよ。』(内容は緊急事態宣言の無意味に対する批判であって、決してJRに対する批判ではない)の思いが通じたのか!?とにかく、JR北海道の英断には感謝しかありません。ニセコ号も予定通り9月4日から無事に運転が始まり、胸を撫で下ろしたのでありました…。勿論、乗車するみんながキチンと感染予防対策を講じて、1人でも罹らない、伝染(うつ)さない事を心掛けなければまた運休の嵐になってしまいますからね。
そして訪れた9月9日。この日はニセコ号の運転4日目にあたります(9月7、8は設定ナシ)。残念ながら札幌の朝は小雨が降るあいにくの空模様…。
この日の私は予め休暇を取っており、最寄り駅から学園都市線526M(731系G-105+733系B-113)で札幌駅(7:30着)に出向きます。平日なのでラッシュ時ではありましたが…。
新幹線の関連工事で10番線の北側、11番線(一旦撤去)には改めてコンクリートによる路盤工事が施され、枕木が敷かれています。来年10月から11番ホーム(ホームとしては32年振りの復活となる)の使用が開始され、新幹線用地となる1番線は廃止になる模様です。
私は2番線ホームに移動し、今回乗車するニセコ号1号車の乗車口札の下で待ちます。
既に1人の乗り鉄オジサンが待っていました。
実は…!この日はテツ友さんとの2人旅です。
ノースレインボー大大大スキ~🤩💕という、今や私のマブダチともいえる旭川在住のらんちゃん様(4月24日のラベンダー編成お披露目で初会い)。彼女はニセコ号が発着する2番線のお隣、1番線に7:25に到着した3004M特急ライラック4号(789系HE-106+HE-206)で到着。しかし…まだ私のもとには現れません…。
8012D臨時特急ニセコは、2015年の登場以来札幌駅を7:57に発車するダイヤが続いています。ちょうど朝ラッシュ時の過密ダイヤのため、発車10分前の段階でもまだ入線していません。LED発車標には、特定の座席が使用不可(窓ガラスの汚損だったらしい…)のため、席移動の旨がスクロール表示されていました。
ニセコ号のNRE編成は7:52位に2番線に入線。つまり発車約5分前!のんびり撮影しているヒマもなく、かなり慌ただしい思いをさせられます…。
切符の画像の通り、今回席を確保したのは最後尾1号車(キハ183-5202)。一昨年夏のフララベンや昨秋のサロベツ4号代走でも乗車した車両です。
実は…!最前部ではありませんが、最後部展望席を同行のらんちゃん様が10時打ちで2名分ゲットしてくださいました!(ひたすら感謝)座席を回転させて後向きで後面展望を楽しませて頂く事にします。そのらんちゃん様は発車近くにようやく私と合流しました。彼女は先頭1号車側から順に撮影をしていたとの事でした…😅
この日の乗車率は指定席でだいたい40~50%位か?前日にえきねっとのシートマップを見る限りでは、通路側もある程度席が埋まってるように見えたのですが…。列車の性格上、乗客は乗り鉄が大半で、どの日程にも道外から客がかなり乗っているように思われます。まぁこのご時世に乗りに来るんだから、皆さん感染予防対策には気を遣ってるでしょうが…。
7:57、札幌駅を発車。残念ながらフロントスクリーンの窓ガラスには雨粒による水滴が付着してしまっており、最後部なのでワイパーを回す事もありませんが、この時点ではほぼ止んでいたようで、少しずつ水滴は解消されていったのでした。
車内放送では、『アルプスの牧場』のオルゴールが!(しかもフルで!)音鉄にとっても嬉しい計らいです♪始発駅発車後以外にも、時折主要駅到着の際に鳴らしてくれました。
余談ですが、新製車両で受話器内蔵型の気動車用オルゴールを装着した車両は、このNRE編成が最後になるのです(一般のキハ183系と放送装置のシステムが同様のため)。
(走行写真は後日桑園駅にて撮影)
最初の停車駅、通勤通学の朝ラッシュの最中にある手稲駅に到着。
去年私は、下り札幌行のニセコ号をここから1区間(しかも指定席!)だけ乗車しています…。
列車は札幌市内を抜け、後志管内(小樽市)に入り銭函駅通過後に石狩湾(小樽湾)の海岸線沿いに出ます。
コチラは進行右側に海が見える区間。銭函~朝里で車窓の見どころともいえる張碓海岸の恵比寿岩(恵比寿島ともいう)が見えます。
朝里~小樽築港の東小樽海水浴場付近(昔むかしの子供の頃、特急北海やED76牽引の客車列車など、行き交う列車を眺めながら海水浴をした事がある…)。この日の天気予報は週間天気の時点で一時期雨マークが付く程あいにくの天気が予想されていましたが、当日になってみれば雨のち曇りという予報に。雨といっても朝の早い時間だけだったようで、この時点になるとご覧の通り、晴れ間が覗いてきました!
同行のらんちゃん様は自分では認めていないものの、私も含めてお友達からは晴れ女と認定されており、その効果もあったのか!?尚、彼女曰く晴れ女パワーは外に出てる間でないと発揮しないとの事ですが…。
8:40、小樽駅2番線に到着。ここで約4分停車します。
らんちゃん様は駅舎側の4番線ホーム(裕次郎ホーム)側に廻って撮影してきたそうですが、私はおとなしく2番線ホーム側のみで撮影…。
小樽駅停車中に撮影した1号車キハ183-5202の出入り口付近。確かに、屋根も含めて白さが際立ってます✨
小樽駅を発車後はいわゆる『山線』と呼ばれる単線区間に入り、険しい峠越えが続きます。
オタモイ峠を越え、塩谷駅を通過、そして蘭島駅で然別駅発の普通1927D(H100形2連)と列車交換します。
蘭島のお隣、余市駅(2番線)には9:07に到着。ここで約9分程停車します。
停車時間の間、観光協会による地元特産品(アップルパイなど)の販売、ご当地キャラ『ソーラン武士』(ソーラン節発祥の地である事と、地元で栽培されるリンゴに因み、かつて豊漁だったニシンを刀に見立てている)のお出迎えで乗客を楽しませてくれます。
鉄道ファンにとってはこの時間は絶好の撮影タイム。
跨線橋を通って反対側の1番線ホームに廻り、編成写真を撮影します。この日は薄曇りで日差しがキツくなかったため、余計な影ができずに済みました(完全な晴天だと逆光になり、先頭部に中途半端な影ができてしまう)。
跨線橋の手摺には、ニセコ号の乗車位置が書かれた案内が掲示されていました。
9:16、ソーラン武士と観光協会の方々のお見送りを受けて余市駅を発車。
余市駅を出ると、稲穂が実る水田地帯や果樹園の中を走ります。
(1枚目は余市~仁木、2枚目は仁木~銀山)
そして再び山間部に入り、峠の中腹にある銀山駅を通過します。
列車はそのまま山間部を進み、かつて岩内線が接続した小沢駅に運転停車。1933Dと列車交換します(発車後の撮影)。
倶知安峠を越え、山線区間の中枢ともいえる倶知安駅2番線に到着します(10:01)。
当駅は2031年開業予定の北海道新幹線の停車駅となっており、現在のホームを撤去した跡に新幹線駅が建設される事になっています。そのため、駅西側には在来線の新ホームが建設されており、10月31日に切り替えられるため現在のホームからのニセコ号発着は今シーズンで最後となりました。
ただ…山線区間は新幹線開業後3セク化されずバス転換される事が取り沙汰されており、もしそうなってしまった場合、新設した在来線駅施設も短命に終わってしまうのでしょうか…。2000年の有珠山噴火の教訓から、山線区間は貨物列車の迂回路として残しておいたほうが良いと考えますが、線路を残しておくだけでも多大な赤字であるだけに、悩ましい処ではあります。
倶知安駅では2分半程度の停車時間しかないため、車内放送では駅舎側に出ないように…というお願いがされていました。そのため私はおとなしく車内に留まる事に…。
向かい側3番線には、H100のトップナンバーが停車中。この後10:18に発車する蘭越行1932Dの車両でしょうか。同列車は通常9:50の発車ですが、特急ニセコの運転日は運転時刻が大幅に繰り下げられています。
10:04に倶知安駅を発車。跨線橋と現ホームも、10月30日を以てその役目を終える事になります。構内入口側には新ホームへ通じる線路が既に敷かれており、10月30~31日の間に一部列車を運休した上で切り替え工事が行われます。
倶知安駅から次のニセコ駅までの間、(株)ニセコリゾート観光協会のスタッフが乗り込み車内販売が実施されます。メニューは写真の通りですが、私はその中から「のむヨーグルト」「かぼちゃクッキー」「あんこカスタード」「ダチョウどら焼」を購入しました。特に「のむヨーグルト」は濃厚な味わいと程よい酸味がチーズケーキのようなスイーツに良く合い、「ダチョウどら焼」(鶏卵の代わりにダチョウの卵を使用)はニセコ号乗車の度に買っており、普通のどら焼の1.5倍位の大きさで結構食べ応えがあります。
ところで、倶知安駅を発車後に車窓から眺める事ができるハズの羊蹄山ですが、残念ながら半分程度が雲に隠れてしまっており、その麗姿をまともに眺める事はできませんでした…(涙)。
10:17、この列車の愛称と同じ名前のニセコ駅に到着。
車販を担当したニセコリゾート観光協会のスタッフが下車し、お見送りを受けます。
ニセコ駅発車後すぐに進行左側に見えるのが、保存されているSL9600形9643号。そのお隣には2017年に引退となったニセコエクスプレス(EXP)の先頭車キハ183-5001が保存されている木造の車庫があります(コロナ禍の影響で現在非公開)。そのニセコEXP、特急ニセコ号(2014~2016シーズンに投入)運用時の冷房装置の故障がとどめを刺したと言われていますが、このニセコ号のNRE車の5号車も後日に冷房故障が発生したとかで…。思えば、ニセコEXPも29年で引退、NREも現在の車齢が29年…。まさか、冷房故障をキッカケに引退時期が早まらなければいいのですが…!?せっかく外装もキレイにリフレッシュしたんだから…。
ここで、気分転換として私は3号車1階席のラウンジに行ってみる事に。
ラウンジは発車時~余市あたりまでは混んでいたように見受けられますが、ニセコ駅発車後はすっかりガラガラで、他に女性客が1人いただけでした。4号車寄りの壁には、世界遺産に登録された北海道・北東北の遺跡群のポスターが掲出されていました。
ニセコ駅の次駅、蘭越町の昆布駅(駅裏には昆布温泉『幽泉閣』がある)にも停車しますが乗降客はいなかったようです。
蘭越、目名の両駅を通過し再び深い山間部に入り、1984年3月に廃止となった上目名駅の跡を通過します。写真に見えるスノーシェッドの奥側のカーブが、かつての駅のあった場所でした。JR北海道の車内誌『THE JR HOKKAIDO』の連載記事『北の鉄道風景』の著者で北海道撮り鉄界の重鎮である眞船直樹氏は、かつて駅があった頃に撮影のためよく通い詰めていたとの事で、廃駅となる前の営業最終日の最後の乗客は、彼の一家だったそうです。
山間部を下り熱郛駅を通過後、後志管内としては最南端のマチの玄関口である黒松内駅に到着。国鉄時代は特急北海や急行ニセコの停車駅で、長万部からお隣熱郛駅を結ぶ区間列車もあったのですが、今では減便に次ぐ減便で当駅に発着する定期列車が下り4本、上り5本という少なさに…。
明治生まれの駅らしく、レンガ造りの危険物庫が残っています。かつては日本海側に抜ける私鉄・寿都鉄道の分岐駅でもありました。
列車は後志管内から渡島管内(長万部町)に入り、日本中JR駅を五十音順に並べると最後になっていた蕨岱駅の跡を通過…。
札幌を出て3時間半、山線区間の旅が終わり11:27、長万部駅に到着します。
ここ長万部駅の名物は『かなやのかにめし』。今では駅構内での立ち売りもなくなり、車内販売の営業も終了したため列車内で食べるには駅前のかなやの店舗に買いに走る必要があるのですが、ニセコ号運転期間中だけの特別なサービスとして、事前予約した人に限りホーム上で買う事ができるのです。実はらんちゃん様が、誕生日祝いとして私の分までも予約して頂いて…。嬉しかったですよ😉
そして、長万部といえば『まんべくん』!子供を見ると追いかけ回したくなるというちょっとヤバいキャラですが、何とも憎めない存在なんですよね…。
10分の停車を終えて11:37に長万部駅を発車。まんべくんと撮り鉄に見送られながら…。
本当はこの日(9月9日)の行程を全てまとめようと思ったのですが、あまりにも長くなり過ぎてしまうため、いくら「読み応え」がコンセプトの拙ブログでも読者がウンザリしてしまうかと思われるため前・後篇と分割させて頂きました。とりあえず前篇はここまで。長万部駅以降の行程は次回にお送りします。
つづく