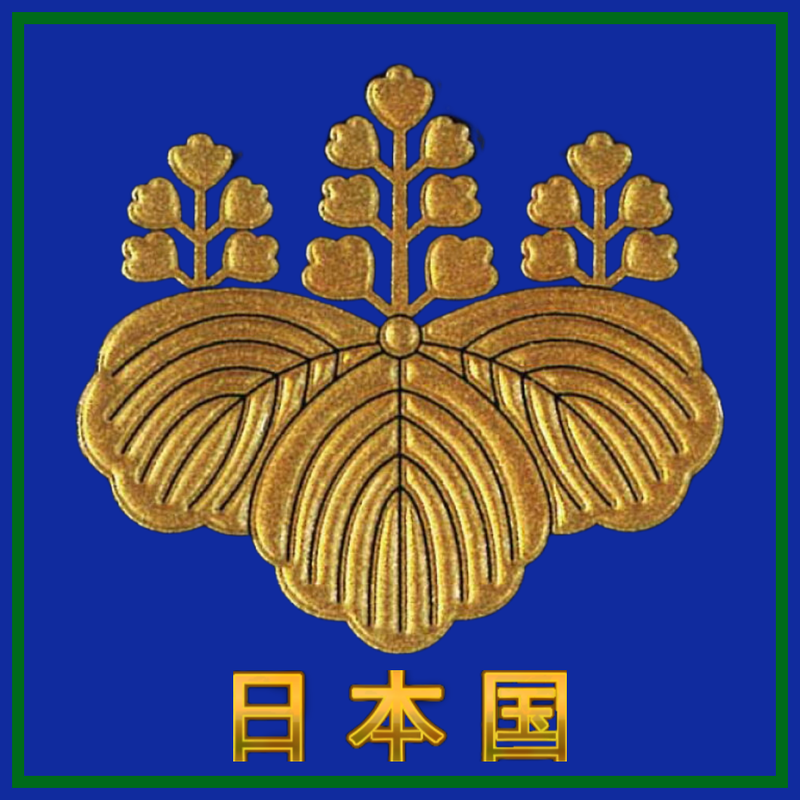安芸もみじ ─ Photographs, Historys, Railways,-JAPAN┃広島
広島発信のブログです。 基本的に「被爆2世が語る平和記念日と世界史」のためのブログなのですが、それでは年に数日の更新に陥ってしまうので。 日頃は鉄道や日記で雑談をUPしつつ、気分がノッてる日には郷土史や歴史関係をユルく語っています。---安芸もみじ⛩️広島
ブログ内検索
プロフィール
テーマ
最新の記事
カレンダー
ブックマーク
月別
2021年06月27日(日) 21時00分00秒
芸備線 と 持続不能の日本・その4
テーマ:機動車•DC・HV etc.岡山駅の10番ホームを発着する、吉備線のキハ40系です。
将来的にはライトレール化される予定で、この景色は見られなくなる見込みなため、撮っておいてみました。
LRT化は約10年程度先の未来ではありますが、こういう風景に限って先送りすると、後回し後回しとなって気が付くと・・・・となってしまうことが多いものです。
しかしJR西日本と総社市、岡山市は3者協議を一時中断すると発表。
都市間輸送路線の割には利用率が低迷していた吉備線を、岡山市内線と総合乗り入れなどで利用客のニーズに合わせようと、LRT化は2018年4月に3者間で合意していました。
低床車両導入のほか8駅の新設、便数増などで利便向上を図り、初期投資額約240億円は3者で分担し、運行本数などを決める"基本計画"の2019年度中策定を目指していましたが、新型コロナウイルスの影響などで遅れていました。
コロナ禍による収益悪化が著しいJR西日本と、岡山市・総社市も税収の大幅減などが見込まれるため、水面下で対応を協議した結果、事業支出が増大する局面に入ることも考慮し、一時中断となったようです。
吉備線のLRT化は既成の決定事項であり、JR路線としては廃線となり、この中断を以て第三セクターへの変換に変更は無いと発表されています。
一方、廃線の危機として取り上げられている芸備線ですが、山間都市の人口減少に伴いその周辺集落も廃町の憂いに遭っている上に、整備不良によって落石警戒のためスピードを落とす区間が増えて所要時間が延びる一方となっています。
今更ですが芸備線は、岡山県新見市の備中神代駅と広島市南区の広島駅を結ぶ、中国山地に沿った全長159.1kmの路線で、1936(昭和11)年10月10日に全通しました。
現在、JR西日本が公表しているデータを見ると芸備線の1日あたりの輸送密度は、広島~三次間は8,817人で、今回維持困難区間として協議対象となっている備中神代~三次間は278人となっていてます。
しかし全線を通した輸送密度は1341人となり、JR北海道 富良野線の1505人と比べてやや少ないとは言え、遜色の無い利用数と言えます。
備中神代~三次間の278人も同じくJR北海道 根室本線・釧路~根室間の250人よりやや多いものの同等で、今後のあり方次第で存続は充分可能と言えます。
ただ芸備線の現在の数字は、1987(昭和62)年のJR西日本発足時よりほぼ50%減少した数字でもあり、少子化問題と併せ山間都市の過疎化が止まらない以上、国の政策と連携した抜本的な構造改革は必要でもあります。
JR西日本が6月14日に岡山県新見市と広島県庄原市に対して『地域公共交通計画に関する申入れ』を行なったと報じられていますが、実際には岡山県と広島県や広島市を含めた全自治体と協議を行う方針としています。
そんな中、芸備線の区間廃止を念頭に今後のあり方の協議と言う話しが広まり、広島県 湯崎知事が『活性化による蘇生が協議の主旨と聞いている。廃線前提とは聞いていない』と、会談を許否しました。
これに対してJR西日本は『廃線前提の協議会ではないので、協議に応じて欲しい』と打診し、7月の協議開始に調整が始まっています。
芸備線が国有化される以前、芸備鉄道は並行道路を走るバスとの競合対策で、駅以外に集落のある場所へ停留所を新設したり、1936年に至るまでほぼ毎年のように気動車を大量増備し、宇品線借り入れ運転など、旅客誘致策にその機動性を活用しました。
時代が違うので取り巻く状況も異なりますが、存続に向けた新しい取り組みが功を成せば、全国の過疎路線へのモデルケースとなる可能性も秘めています。
さて、私個人的には閉園した加悦SL広場のキハユニ51は、かつて芸備鉄道のキハユニ18で、未だに引き取り先が決まらず解体の噂も出ている状況です。
こういった産業遺産も広島へ連れて帰って来て、芸備線活性化とリンクして有効活用を見出だすことも、必要な施策の1つとなるのではないかと考えます。
▼本日限定!ブログスタンプ
旅をするなら船派?飛行機派?
2021(令和3)6月28日は貿易記念日。
1859(安政5)年5月28日、徳川幕府がアメリカ・イギリス・フランス・ロシア・オランダの5ヶ国との間に結んだ友好通商条約に基づき、横浜・長崎・箱館(函館)の各港で自由貿易の開始を布告しました。
これを記念して、日付を太陽暦に換算した今日を記念日に、1963(昭和38)年に制定されまた。
貿易記念日は貨物の流通のみでなく、為替や旅客など、事実上の鎖国解除でもありました。
旅をするなら船派と言いたいところですが、時間と経費を考えると飛行機派と言わざるを得ないものです。
が、国内なら鉄道派と言えるかも知れません。