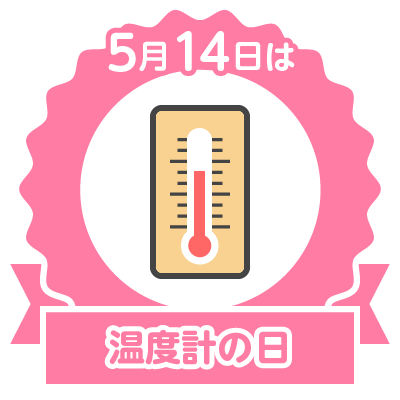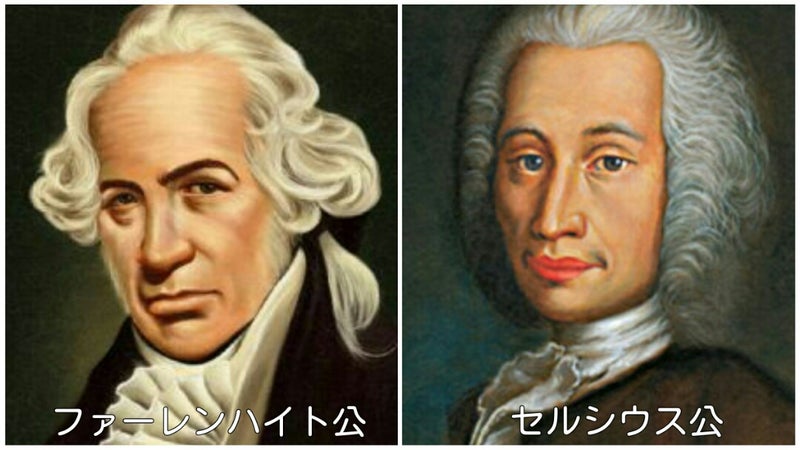安芸もみじ ─ Photographs, Historys, Railways,-JAPAN┃広島
広島発信のブログです。 基本的に「被爆2世が語る平和記念日と世界史」のためのブログなのですが、それでは年に数日の更新に陥ってしまうので。 日頃は鉄道や日記で雑談をUPしつつ、気分がノッてる日には郷土史や歴史関係をユルく語っています。---安芸もみじ⛩️広島
ブログ内検索
プロフィール
テーマ
最新の記事
カレンダー
ブックマーク
月別
2021年05月13日(木) 20時30分00秒
広電宮島線をスマホでチョイ撮り
テーマ:JNR•JRの車両じゃないいろいろ時々、スマホでチョイ撮りして貯まった、広電電車の写真をUPしてみました。
撮影したのは昨年の6月~12月。
たまにはこういうラフな記事も良いかなぁと。
モロ逆光での写真ですが、スマホも頑張って写らせてくれました。
私のスマホはもう年代モノで、2015年6月19日発売のSH-04Gです。
NTTドコモの第3.9世代移動通信システム = Xi と、第3世代移動通信システム = FOMA とのデュアルモード端末で、第2期ドコモスマートフォン。
解像度HD = 720 ×1280、画素数 = 1310万となっていますが、速写性に関してはちょっと難アリな機種です。
さて、この辺りは山から流れて来る小川が古来より数多くあり、江戸時代から住宅地化する過程で水路として整備されましたが、21世紀の今はボックスカルバートとなっています。
しかし明治時代に敷設された山陽本線と、大正時代に敷設された宮島線の周辺では、一部が水路時代のまま露出していて。
そこには、恐らく江戸時代のままの水澤草が生息しており、狐の灯籠が実っていたので撮ってみました。
狐の灯籠とは蒲の穂のことで、これは実ではなくフランクフルトみたいな形態をして、花だったりします。
蒲は古から、若葉は食用とされ花粉は傷薬や漢方薬、葉や茎は筵や簾の材料、穂を乾燥させて虫除けとして利用されていました・・・・って、漢字が難しい?
『蒲』は『がま』、『筵』は『むしろ』、『簾』は『すだれ』ですよ。
1枚だけ途中、高須駅周辺ではなく新井口駅に隣接する商工センター駅での写真です。
そしてラスト2枚は高須駅下りホームでの京急色の3903号ですが、発車した電車の流し撮りを失敗しました。
▼本日限定!ブログスタンプ
暑いのと寒いの、どっちが好き?
さて、今回は鉄道線である宮島線の写真でしたが、広島電鉄と言えばやはり軌道線。
道路を走る路面電車ですが、道路と言えば交通標識。
なので、面白いと感じた動画がTwitterにあったので、リツイートをリンクしてみました。
回転式可動標識、最近は見かけなくなりましたが、少し前まで近所(宮島街道)にもありました。
— 源 真琴 (@miyashima_0405) 2021年5月12日
が、動くところ初めて見ました。 https://t.co/WweFNNpVXj
そして、今日は温度計の日。
人類史上初の温度計は1600年頃、イタリアの物理学者ガリレオ・ガリレイが発明した空気温度計で、液体の密度は温度に比例して変化する原理を発見したことから、この温度計が生まれました。
しかしこの原始的な温度計は、気温だけでなく気圧にも反応することから実用化には至らず、正確な温度が計測できる温度計は、約100年の時を待たなければ登場できませんでした。
そして水銀を使用した計測器を発明したドイツの物理学者ガブリエル・ファーレンハイトが、1724年に温度の定義を定めて目盛りを振ったものが、華氏温度計です。
しかし水銀温度計の計測能力は正確であっあものの、ファーレンハイトの定めた定義が正確性に欠けたため、水の沸点を100度、融点を0度とした摂氏温度計が1742年にスウェーデンの物理学者アンデルス・セルシウスによって定義付けられます。
その後、華氏温度も正確な定義が考察され、現代では『摂氏温度 × 1.8 + 32 = 華氏温度』の公式で、変換することができます。
ちなみに平賀源内(ひらがげんない)公が1765年に作った"日本創製寒熱昇降器"と名付けられた温度計には、数字と並記されて『極寒・寒・冷・平・暖・暑・極暑』と記されていましたが、採用されていた基準は華氏でした。
尚、華氏は°F、摂氏は°Cの単位で表記されますが、摂氏はセルシウス氏から転意したもので、ファーレンハイトは中国語で華倫海氏と記されたことから、華氏と呼ばれます。
さて温度計の日の由来ですが、温度計を実用化し普及させたファーレンハイトの誕生日、1686年5月14日に因んでいますが、温度計の日は日本独自の非公式記念日です。
| ・ | ・ |
 | ゑ |  |